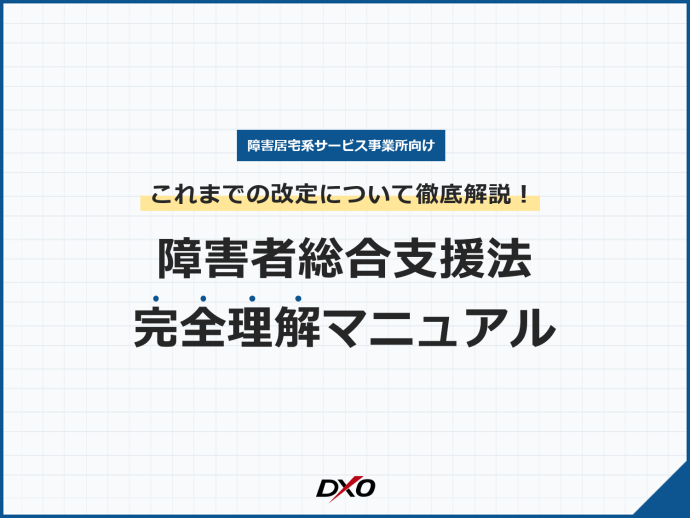「障害者総合支援法って何?」「どんなサービスが対象なの?」
このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
今回の記事では、障害者総合支援法について、対象者や目的、サービス内容などについて詳しく解説します。
目次
障害者総合支援法とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の通称です。
この法律は、障害者や障害児の方が、障害を抱えながらも尊厳を保ち、住み慣れた地域で生活ができるように支えることを目的としています。
社会情勢がめまぐるしく変化することが考えられるため、障害者や障害児、支援者のニーズの変化に適応できるよう、3年ごとに定期的な改正があります。
障害者総合支援法の対象となる方は以下になります。
①18歳以上で身体・知的・精神のいずれかに障害のある方(発達障害者を含む)
②障害児…18歳未満で身体・知的・精神のいずれかに障害のある児童(発達障害児を含む)
③難病患者…障害者総合支援法で指定されている難病を患っている患者(障害者手帳を所持していなくても対象となることがある)
障害者総合支援法の目的は「障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活または社会生活を営む」ことです。
基本理念には以下の6つを掲げています。
①障害者も他の国民同様に個人として尊重される
②障害の有無に関係なく相互に人格と個性を尊重し合える共生社会を実現する
③障害者・障害児が可能な限り身近な場所で支援を受けられること
④社会参加の機会が確保されること
⑤どこで誰と住むかなど他者との共生が妨げられないこと
⑥障害者・障害児が社会生活をする上での障壁の除去に資すること
これらの目的や理念を簡単にまとめると、障害を持っている方でも他の国民と同じように尊重され、生活を営めるようにすることを目標しています。
障害者総合支援法は、
①介護給付サービス
②訓練等給付サービス
③自立支援医療サービス
④相談支援サービス
⑤その他
の5つに分かれています。
それぞれ解説していきます。
介護給付サービスとは、障害を持っている方に対して介護費用の一部を給付するサービスです。
介護給付サービスの種類は下表の通りです。
| サービス | 対象 | 内容 |
| 居宅介護 | ・障害により自力での日常生活が難しい方 ・障害支援区分が1以上の方 | ・掃除、洗濯、買い物など支援 ・入浴・着脱などの介護 ・通院の介助 |
| 重度訪問介護 | ・障害支援区分が4以上で、二肢以上に麻痺がある方 | ・居宅において入浴や食事などの介護 ・外出時の介護 |
| 同行援護 | ・視力障害により移動が著しく難しい方 | ・外出時に移動時の必要な情報を提供や援助 |
| 行動援護 | ・障害支援区分が3以上である方 | ・危険を回避するための援護 ・外出時の介護 ・排泄および食事の介護 |
| 重度障害者等包括支援 | ・重度訪問介護の対象者で、四肢すべてが麻痺している方 | ・介護給付サービスを包括に提供 |
| 短期入所(ショートステイ) | ・障害支援区分が1以上の方 | ・入所期間内の入浴や食事の介護 |
| 療養介護 | ・障害支援区分が5以上である方 | ・機能訓練や療養上の管理など |
| 生活介護 | ・障害支援区分が3以上の方 ・年齢が50歳以上で、障害支援区分が2以上の方 | ・排泄および食事の介護に関する相談助言 ・創作活動や生産活動の機会提供 |
| 施設入所支援 | ・生活介護を受けていて、障害程度区分が4以上の方 ・生活介護を受けている方で、年齢が50歳以上の障害区分が3以上の方 ・自立訓練や就労移行支援を受けており、入所が必要な方 | ・入浴、排泄、食事などの相談助言や支援を行う |
介護給付サービスとは、障害を持っている方に対して就労に向けた訓練や支援を提供するサービスです。
訓練等給付サービスの種類は以下の通りです。
| サービス | 対象 | 内容 |
| 自立訓練 (機能訓練) | ・地域生活への移行で、リハビリの継続や身体機能の維持や回復が必要な方 | ・居宅訪問による理学療法や作業療法、その他の支援 |
| 自立訓練 (生活訓練) | ・地域生活への移行で、生活能力の維持や向上の支援が必要な方 | ・居宅訪問による入浴、排泄、食事などの訓練や支援 |
| 宿泊型自立訓練 | ・自立訓練の対象者で、一般就労を利用しており、帰宅後の生活能力の維持や向上が必要な方 | ・居室やその他の設備が利用可能 ・家事等の生活能力を向上させる支援 |
| 就労移行支援 | ・就労を希望する65歳未満の障害者であり、一般企業に雇用されると見込まれる方 | ・就労に必要な知識や能力向上の訓練 ・求職活動の支援 |
| 就労継続支援A型(雇用型) | ・就労移行支援事業や支援学校等を利用したが、企業への雇用に結びつかなかった方 | ・就労に必要な知識や能力向上の訓練 |
| 就労継続支援B型(非雇用型) | ・雇用されていたが、年齢や心身の状況などによって、雇用の継続が難しくなった方 | ・就労に必要な知識や能力向上の訓練 |
| 就労定着支援 | 就労移行支援事業により雇用され6ヶ月たった方 | ・雇用したことによって生じた問題に関する相談助言や支援 |
| 自立生活援助 | 居宅において単身のため、自立した生活が営めない方 | ・定期的な巡回訪問 ・居宅における生活の問題に関する相談助言 |
| 共同生活援助 (グループホーム) | 障害者(身体障害者は65歳未満) | ・共同生活による相談、入浴、食事などの援助 |
自立支援医療とは、障害を持っている方に対して医療費の自己負担額を軽減する公費負担制度になります。
自立支援医療サービスとは以下の3つの制度を一元化した新制度になります。
| 制度 | 内容 |
| 育成医療 | 身体障害のある児童を対象に、障害を改善するための生活能力を得るための医療費の自己負担を軽減する |
| 更生医療 | 身体障害のある方を対象に、障害を改善するための生活能力を得るための医療費の自己負担を軽減する |
| 精神通院医療 | 精神疾患(てんかんを含む)の方を対象に、精神科の通院医療費の自己負担を軽減する |
相談支援サービスでは、障害を持っている方が障害による日常生活での悩みを相談することができます。
相談支援サービスの種類は以下の通りです。
| 種類 | 内容 |
| 基本相談支援 | 幅広い相談に応じる支援 |
| 地域移行支援 | 障害者支援施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等を退所する障害者を対象として、地域移行支援計画の作成、外出の同行支援 |
| 地域定着支援 | 居宅において単身で生活している障害者を対象に、連絡体制の確保や緊急時の支援 |
| サービス利用支援 | 障害福祉サービス等の申請に係る利用計画案を作成、支給決定後のサービス事業者との連絡調整 |
| 継続サービス利用支援 | サービス支給決定後の利用状況の検証、サービス事業者との連絡調整 |
| 障害児支援利用援助 | 障害児通所支援の申請に係る利用計画案を作成、支給決定後のサービス事業者との連絡調整 |
| 継続障害児支援利用援助 | サービス支給決定後の利用状況の検証、サービス事業者との連絡調整 |
上記のサービスの他には「地域生活支援事業」や「障害児を対象としたサービス」があります。
それぞれ解説していきます。
地域生活支援事業は「市町村事業」と「都道府県事業」の二つに分かれています。
「市町村事業」の種類は以下の通りです。
| 事業 | 内容 |
| 理解促進研修・啓発 | 障害者に対する理解を深める研究や啓発 |
| 自発的活動支援 | 障害者やその家族に対して自発的に行う支援 |
| 相談支援 | 相談に応じ、情報提供や権利擁護の援助を行う |
| 基幹相談支援センター等の機能強化 | 総合的な相談事務の実施、地域の相談体制の強化 |
| 成年後見制度利用支援 | 補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難な方に、費用を助成 |
| 成年後見制度法人後見支援 | 市民後見人を活用した法人後見を支援するための研修を行う |
| 意思疎通支援 | 意思疎通が困難な方の仲介をするために、手話や通訳、点訳の派遣を行う |
| 日常生活用具給付等 | 自立生活支援用具等の給付または貸与 |
| 手話奉仕員養成研修 | 手話での意思疎通支援 |
| 移動支援 | 屋外での移動が困難な方への外出支援 |
| 地域活動支援センター | 創作活動や生産活動の提供、社会との交流促進 |
| その他(任意事業) | 福祉ホームの運営、訪問入浴サービス、日中一時支援など |
日常生活用具給付等の自立生活支援用具等の給付または貸与では、補聴器の給付が行われています。
「都道府県事業」の種類は以下の通りです。
| 事業 | 内容 |
| 専門性の高い相談支援 | 発達障害、高次脳機能障害などの専門性の高い相談に対し情報提供 |
| 広域的な支援 | 市町村域を超える広範囲の支援 |
| 専門性の高い意思疎通支援を行う養成・派遣 | 専門性の高い意思疎通が可能な者の派遣 |
| 意思疎通支援を行う者を派遣に係る連絡調整 | 手話通訳者や要約筆記者の派遣に係る連絡調整 |
| その他(研修事業を含む) | オストメイト社会適応訓練、音声機能障害者発声訓練、発達障害者支援体制整備など |
障害児を対象としたサービスも「市町村」と「都道府県」の二つに分かれています。
「市町村の障害児を対象としたサービス」の種類は以下の通りです。
| サービス | 内容 |
| 児童発達支援センター | 地域で生活する障害児や家族への支援、地域の障害児を預かる施設に対する支援 |
| 児童発達支援事業 | 通所利用の未就学の障害児に対する支援療育 |
| 放課後等デイサービス | 就学中の障害児が放課後や長期期間中に、生活能力を向上させるための訓練を行うと共に居場所作りを促進する |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害により外出が困難な障害児の居宅に訪問、支援を行う |
| 保育所等訪問支援 | 訪問により、集団生活へ適応するための専門的な支援を行う |
「都道府県の障害児を対象としたサービス」は以下の通りです。
| サービス | 内容 |
| 福祉型障害児入所施設 | 施設に入所している障害児への日常生活の知識や技能を付与を行う |
| 医療型障害児入所施設 | 施設や医療機関に入所している障害児への日常生活の知識や技能を付与、治療を行う |
2006年に施行された障害者自立支援法が、2013年に改定されて障害者総合支援法となりました。
障害者総合支援法は、障害者自立支援法の問題点を解消するために新しく作られたものと言えます。
障害者自立支援法から障害者総合支援法へと、どのように変更されたかはこちらの記事で詳しく解説しています。
障害者自立支援法と障害者総合支援法とは?違いは?それぞれの特徴についてご紹介!
障害者総合支援法は3年に1度、障害者や障害児、支援者のニーズの変化に適応できるように、障害福祉サービス等報酬改定によって改定されます。
障害者総合支援法の問題点として下記の3つが挙げられます。
①利用者負担の所得計算が世帯単位であること
②介護保険サービス利用者負担軽減制度の妥当性
③利用者負担が応能負担であること
詳しくはこちらの記事で解説しています。
障害者福祉サービスの利用料金は、世帯全体の収入によって異なっていますが、最大でも1割負担となります。
所得を判断する世帯の範囲は下表のとおりです。
| 種別 | 世帯の範囲 |
| 18歳以上の障害者 (施設に入所する18,19歳を除く) | 障害のある方とその配偶者 |
| 障害児 (施設に入所する18,19歳を含む) | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
上の表の世帯の範囲の収入状況によって、4つに区分けされ、それぞれに自己負担の上限月額が設定されています。
ひと月に利用したサービス量に関係なく負担上限額を超えて利用料を支払う必要はありません。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円(未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者除く | 9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
参考:厚生労働省
障害者サービスを利用する場合の窓口は市区町村の担当課となります。
ただし介護給付と訓練給付は流れが異なるので注意しましょう。
1.市区町村の窓口で利用申請
2.障害支援区分の認定が必要です
3.サービス等利用計画案の作成と提出
4.支給決定
5.利用開始
1.市区町村の窓口で利用申請
2.サービス等利用計画案の作成と提出
3.暫定支給決定
4.支給決定
5.利用開始
介護給付、訓練給付はいずれも利用開始後に見直しをおこない、必要があれば計画の修正がおこなわれます。
障害のある方のニーズやペースにあった支援が重視されています。
今回の記事では、障害者総合支援法について、対象者や目的、サービス内容などについて解説しました。
障害者総合支援法について理解を深め、障害者の方がより充実した生活が送れる世の中にしていきましょう。