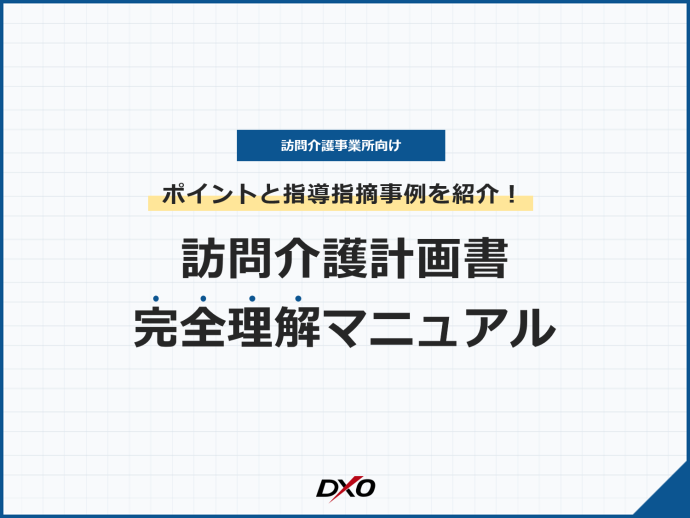介護福祉士やホームヘルパーなどが自宅を訪問して生活を支援する訪問介護サービスは、支援内容によって「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」に分けられています。
今回の記事では、家事などをサポートする生活援助について、身体介護との違いにふれながら、具体的な支援内容やサービスを提供する際の注意点について解説します。
目次
生活援助とは、利用者が日常生活を営むことを支援するサービスのことです。具体的には以下のような支援が挙げられます。
身体介護とは、利用者の身体に直接触れておこなうサービスのことです。具体的には以下のような支援が挙げられます。
詳しくは以下の記事で解説しているのであわせて参考にしてください。

身体介護とは?サービス内容や費用・生活援助との違いを詳しく解説!
訪問介護は、サービスの提供時間によって区分があります。身体介護では「身体1~5」の5段階、生活援助では「生活1~3」の3段階に分けられています。
「身体1生活1」とは、身体介護、生活援助サービスの利用時間がそれぞれもっとも短い段階のことを指します。
身体1は、1日20分以上30分未満のサービスと定められています。利用者が希望する支援や介助が少なく、30分未満で終わる場合は身体1としてサービスを提供します。
入浴介助や移動介助など複数の介護を依頼する場合には、サービス時間ごとに各段階が適応されます。身体介護の5段階の提供時間と加算の単位数は以下の通りです。
| サービス提供時間 | 単位数 | |
| 身体1 | 20分以上30分未満 | 163単位 |
| 身体2 | 30分以上1時間未満 | 387単位 |
| 身体3 | 1時間以上1時間30分未満 | 567単位 |
| 身体4 | 1時間30分以上2時間未満 | 649単位 |
| 身体5 | 2時間以上2時間30分未満 | 731単位 |
生活2とは、以下の区分でのサービスのことを指します。身体介護と同様に利用者の依頼によって必要な時間を設定します。生活援助の段階ごとの提供時間と加算の単位数は以下の通りです。
| サービス提供時間 | 単位数 | |
| 生活援助2 | 20分以上45分未満 | 179単位 |
| 生活援助3 | 45分以上 | 220単位 |
訪問介護の生活援助は、要介護1~5の認定を受けている方は利用することができます。同居家族がいる方は、やむを得ない事情がある場合に限り生活援助を受けられます。やむをえない事情と認められる例、認められない例は以下の通りです。
【やむをえない事情と認められる例】
【やむをえない事情と認められない例】
ただし、市町村によっては、同居家族がいると生活援助のサービスを利用できないと定めている所もあるので確認が必要です。
訪問介護の生活援助は、要介護度ごとに厚生労働省によって1か月間の利用回数が制限されています。
| 要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 利用回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
1回の訪問介護で、身体介護と生活援助を両方行う場合は、回数には含まないことになっています。
場合によっては、規定の回数以上のサービスを提供しなければならないこともあるかもしれません。その場合、介護支援専門員は、市町村に対して届け出を行う必要があります。
生活援助中心型の算定には、厚生労働省による「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」によって、具体的な算定理由を記載する必要があります。定型的な文章では理由として認められなくなりました。
上記のように、詳しく理由を記載しましょう。独居の場合や、家族が障害・疾病でサービスが必要である場合であったとしても、本人ができる部分、できない部分を評価したうえでのサービス提供がされているか、障害の程度に妥当な保険給付かどうかを明記する必要があります。
訪問介護の生活援助は、要介護度ごとに厚生労働省によって1か月間の利用回数が制限されています。
| 要介護度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 利用回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
1回の訪問介護で、身体介護と生活援助を両方行う場合は、回数には含まないことになっています。
身体介護中心型の訪問介護では、身体的なケアや介助が中心になります。入浴、排泄、食事、移動などの日常生活の介助を行います。より詳細なケアを提供します。
生活援助中心型の訪問介護は、日常生活全般をサポートします。食事の準備、掃除、買い物、社会的交流などを調整していきます。自治体によってサービスの提供範囲が異なるため、ケアマネージャーに確認しましょう。以下は、訪問看護において職員ができることとできないことの例です。
| 介護内容 | できること | できないこと |
| 掃除 |
|
|
| 洗濯 |
|
|
| 調理 |
|
|
| 買い物 |
|
|
| 外出支援 |
|
|
| その他 |
|
|
生活援助で行えるサービスは以下の通りです。
また、以下は生活援助のサービスには含まれないので注意しましょう。
生活援助中心型とは、身体介護よりも生活援助の割合が中心になるサービスという意味合いであり、身体介護を行うこともあります。例えば、利用者の居室を掃除する際には、利用者を寝室からリビングまで移動させるため、体に触れる身体介護を行うこともあるでしょう。
訪問介護の生活援助中心型では、家事などのサービスを提供することで、利用者が住み慣れた自宅で自立した日常生活を維持することが期待されます。利用者の依頼によるサービスであり、個人のニーズに合わせてサービスを提供し、利用者家族の負担軽減にもつながります。
しかし、利用者の自立支援や重度化を防止するために上限回数が設けられていたり、ケアプランに基づくサービスしか提供できないことになっています。また、家族のためにサービスを提供することはできないなどの決まりがあります。
自治体によっても決まりが異なる可能性があるので、不明な点は担当のケアマネジャーに確認しましょう。