
訪問介護は、高齢者や障害者が自宅で安心して生活できるようサポートするサービスです。しかし、利用には費用がかかるため、どのくらいかかるか不安で利用に踏み切れないという方もいるのではないでしょうか?
そこで、本記事では、訪問介護の利用料金について解説します。費用を抑えるためのポイントについても詳しく紹介するのでぜひ参考にしてください。
目次
訪問介護は、日常生活に支援が必要な高齢者や障害者の方に向けたサービスです。
具体的なサービスには、食事や入浴、排せつなどの介助をおこなう身体介護、家事や買い物の代行をおこなう生活援助、通院時の補助などをおこなう通院等乗降介助の3つがあります。
これらのサービスを受けることで、なるべく無理なく在宅生活を続けることができるようになるため、住み慣れた自宅で老後を過ごしたいという方におすすめです。
なお、訪問介護を利用できるのは要介護1~5の認定を受けた人に限られる点に注意しましょう。
厚生労働省の参考資料によると、1人あたりの訪問介護の料金は、要介護3の方で82,000円程度、要介護5の方で149,000円程度であることがわかります。
ただし、訪問介護の料金は、利用するサービスの内容や頻度、介護度や自己負担割合などさまざまな要素によって異なります。この金額はあくまで目安として覚えておきましょう。
訪問介護の料金は、利用するサービスの内容や頻度、介護度や自己負担割合などによって定まります。以下では料金が決まるポイントについて、それぞれ解説します。
訪問介護の基本費用は、1回のサービス提供時間に応じて計算されます。
サービス提供時間ごとに料金が設定されており、〇分未満、〇分以上〇分未満…といった具合に区分されています。もちろん、サービス提供時間が長くなるほど料金も高くなります。
また、利用するサービスによって料金も異なるので、詳しくは以下の表を参考にしてみましょう。なお、以下で紹介するのは料金であり、1割から3割の自己負担割合を乗じた費用が実際に支払う金額となります。
サービス分類 | 区分 | 料金*1 |
身体介護 | 20分未満 | 1,630円 |
20分以上30分未満 | 2,440円 | |
30分以上1時間未満 | 3,870円 | |
1時間以上*2 | 5,670円 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 1,790円 |
45分以上 | 2,200円 | |
通院等乗降介助 | 1回あたり | 970円 |
*1:1単位=10円として計算
*2:以降30分を増すごとに+820円
訪問介護の利用料金の自己負担割合は、利用者の所得によって異なります。
基本的には、自己負担割合は1割ですが、現役並みの所得がある高齢者の場合、介護保険制度の公平性を確保するために自己負担割合は2割から3割となります。
世帯の状況によっても異なるため、詳しくは以下の表で確認してみましょう。
【世帯に65歳以上の方が1人の場合】
年金収入+その他の合計取得 | 自己負担割合 |
340万円以上 | 3割 |
280万円以上340万円未満 | 2割 |
280万円未満 | 1割 |
【世帯に65歳以上の方が2人以上の場合】
世帯の65歳以上の人の年金収入+その他の合計取得 | 自己負担割合 |
463万円以上 | 3割 |
346万円以上463万円未満 | 2割 |
346万円未満 | 1割 |
*1:第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)、市区町村民税非課税の方、生活保護受給者は1割負担
訪問介護の料金には、提供されるサービス内容に応じて加算が行われることがあります。
例えば、夜間や早朝のサービス、医療的ケアが必要な場合など、特定の条件下でのサービスには追加料金が発生します。
加算名 | 加算の要件 | 加算される料金 |
初回加算 | はじめて訪問介護を利用する場合 | 2,000円/月 |
2人以上の訪問介護員等によるサービス提供 | 2人以上の訪問介護員等によるサービスを受ける場合 | 基本料金の100%/回 |
夜間もしくは早朝のサービス提供 | 夜間(18時から22時まで)または早朝(6時から8時まで)に訪問介護を利用する場合 | 基本料金の25%/回 |
深夜のサービス提供 | 深夜(22時から翌6時まで)に訪問介護を利用する場合 | 基本料金の50%/回 |
緊急時訪問介護加算 | 緊急で訪問介護を利用する場合 | 1,000円/回 |
特定事業所加算 | 一定の要件を満たした質の高い訪問介護事業所を利用する場合 | 基本料金の3~23% |

緊急時訪問介護加算とは?単位数や算定要件について徹底解説!
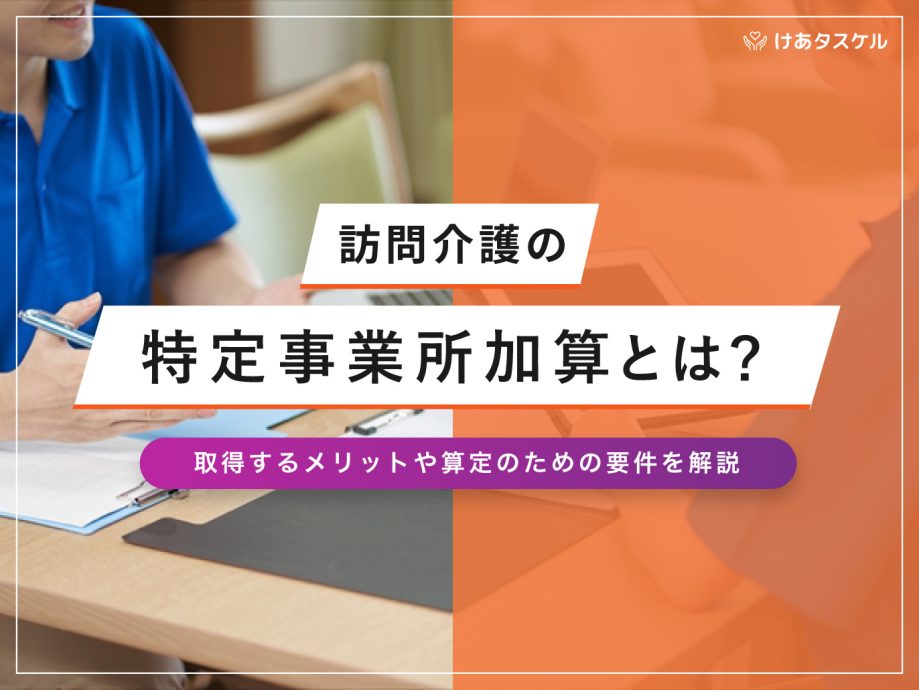
【2024年改定対応】訪問介護の特定事業所加算とは?メリットや算定要件を解説
訪問介護の料金を抑えるためには、以下の制度を活用することが有効です。
高額介護サービス費制度は、一定の自己負担限度額を超えた場合に、その超過分を支給する制度です。この制度を利用することで、訪問介護の自己負担額を軽減することができます。
支給してもらうためには、市区町村への申請が必要になるため、以下の要件を満たしている場合は確認してみましょう。
設定区分 | 対象者 | 負担の上限額(月額) |
第1段階 | 生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) |
第2段階 | 市町村民税世帯非課税で公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
第3段階 | 市町村民税世帯非課税で第1段階および第2段階に該当しない方 | 24,600円(世帯) |
第4段階 | 市区町村民税課税世帯~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) | |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
高額医療・高額介護合算制度は、医療費と介護費を合算し、一定の限度額を超えた場合にその超過分が支給される制度です。医療費と介護費の両方が高額になる場合には、この制度を利用することで負担を軽減できます。
75歳以上 | 70~74歳 | 70歳未満 | ||
介護保険+後期高齢者医療 | 介護保険+被用者保険または国民健康保険 | |||
年収約1,160万円 | 212万円 | |||
年収約770~約1,160万円 | 141万円 | |||
年収約370~約770万円 | 67万円 | |||
~年収約370万円 | 56万円 | 60万円 | ||
市町村民税世帯非課税等 | 31万円 | 34万円 | ||
市町村民税世帯非課税 | 本人のみ | 19万円 | ||
介護利用者が複数 | 31万円 | |||
低所得者向けの利用者負担軽減制度を活用することで、訪問介護の自己負担額を軽減することができます。利用料金の一部を補助してもらうことが可能です。
訪問介護の利用料金や費用を抑えるための制度については、専門知識が必要です。料金について迷った場合や、どの制度を利用すべきか分からない場合は、ケアマネジャーに相談することをおすすめします。ケアマネジャーは、あなたの状況に応じた最適なアドバイスを提供してくれます。
訪問介護の利用料金について理解を深め、必要な支援を受けながら、安心して生活を続けるために、ぜひケアマネジャーと相談しながら進めていきましょう。