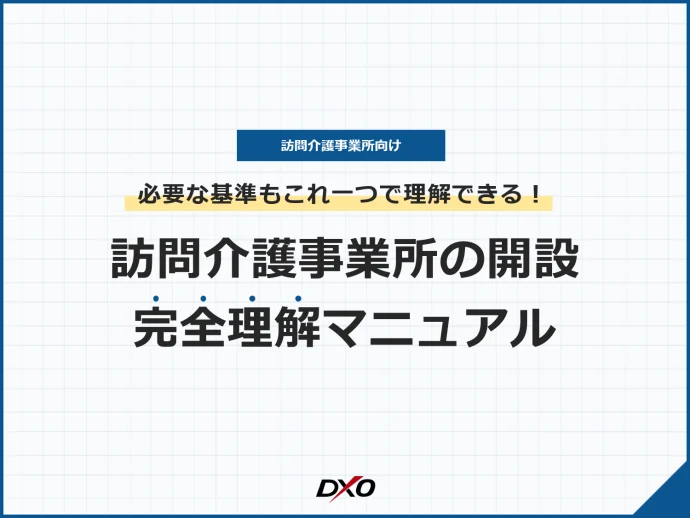「訪問介護の事業所を開業したいけど何をしたらいいか分からない」「訪問介護の事業所を経営するために必要な知識を身に付けたい」「訪問介護事業所で失敗しない方法を知りたい」
今回の記事ではそのような方へ向けて、訪問介護の開業に必要な資格、訪問介護の開業で満たすべき基準、訪問介護の開業のステップなどについて詳しく解説します。
目次
訪問介護のサービス内容は主に、
①身体介護・・・食事、入浴、更衣、排泄など利用者の身体に触れて行う介護
②生活援助・・・掃除、洗濯、調理、買い物などを利用者本人や家族の代わりに行うサービス
③通院時などの乗降介助・・・通院時の送迎、通院先での受診手続き、薬の受け取りなど、利用者の自宅→病院→自宅の移動における介護全般
の3つです。
訪問介護のサービス内容について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
【2022年最新版】訪問介護とは?サービス内容や受け方、費用についてご紹介!
訪問介護の事業所を開業するためには、「訪問介護員」「サービス提供責任者」「管理者」を配置する必要があるため、一人で開業をすることはできません。
訪問介護の事業所を開業するためには、「訪問介護員」「サービス提供責任者」「管理者」を配置する必要があると述べましたが、必要な資格と配置基準は下記の通りです。
| 職種 | 必要な資格 | 配置基準 |
| 訪問介護員 | 介護福祉士 介護職員実務者研修修了者 介護職員初任者研修修了者 旧介護職員基礎研修修了者 旧ホームヘルパー1級、2級 看護師または准看護師 | サービス提供責任者を含めて常勤換算2.5人以上 |
| サービス提供責任者 | 介護福祉士 介護職員実務者研修修了者 旧介護職員基礎研修修了者 旧ホームヘルパー1級 看護師または准看護師 | 3か月間の平均利用者の人数が40人を超えるごとに1人以上追加 |
| 管理者 | なし | 訪問介護事業所の責任者であり、管理の職務に従事する常勤1人 (サービス提供責任者との兼務可能) |
訪問介護に必要な資格について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
訪問介護に必要な資格3選!メリット・費用・取得方法をご紹介
訪問介護事業所として指定されるには、法人格であることに加えて「人員」「設備」「運営」の3つの基準をクリアする必要があります。
訪問介護の事業所を開業するためには、下表の通り、「訪問介護員」「サービス提供責任者」「管理者」の配置が必要です。(上記の表と同じ)
| 職種 | 必要な資格 | 配置基準 |
| 訪問介護員 | 介護福祉士 介護職員実務者研修修了者 介護職員初任者研修修了者 旧介護職員基礎研修修了者 旧ホームヘルパー1級、2級 看護師または准看護師 | サービス提供責任者を含めて常勤換算2.5人以上 |
| サービス提供責任者 | 介護福祉士 介護職員実務者研修修了者 旧介護職員基礎研修修了者 旧ホームヘルパー1級 看護師または准看護師 | 3か月間の平均利用者の人数が40人を超えるごとに1人以上追加 |
| 管理者 | なし | 訪問介護事業所の責任者であり、管理の職務に従事する常勤1人 (サービス提供責任者との兼務可能) |
人員基準についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
訪問介護の開業に必要な人員基準について計算方法など徹底解説!
設備基準は、下表の事務室、相談室、手洗い場、備品の基準をそれぞれ満たす必要があります。
| 設備 | 必要なもの |
| 事務室 | 特に広さに関する規定はなく、必要不可欠な備品を設置できるスペースが確保できれば問題なし 物件を決める際は送迎車の駐車スペースの有無も要確認 |
| 相談室 | 利用者や家族が訪問した際に利用できるスペースとプライバシー保護のための配慮が必要 |
| 手洗い場 | 手洗い可能な洗面所。共有の洗面所しかない場合は、事務所内に手洗い場を設置して許可をとる |
| 備品 | デスク・椅子・相談室用の机と椅子・電話・パソコン・プリンター・キャビネット・カギ付きの書庫・消毒液・石鹸・ペーパータオルなど |
訪問介護の設備基準については、こちらの記事で詳しく解説しています。
訪問介護事業所が知らないといけない『設備基準』とは
運営基準は、下表の「訪問介護サービスに関する基準」と「業務運営に関する基準」をそれぞれ満たす必要があります。
| 基準 | 必要なこと |
| 訪問介護サービスに関する基準 | ・内容、手続きの説明および同意 ・サービスの提供拒否の禁止 ・サービスの提供が困難になった際の対応 ・身分を証する書類の携行 ・緊急、事故発生時などの速やかな対応 |
| 業務運営に関する基準 | ・利用料等の受領方法 ・訪問介護計画書の作成 ・介護等の総合的な提供 |
訪問介護の運営基準については、こちらの記事で詳しく解説しています。
訪問介護事業所が知らないといけない『運営基準』とは
訪問介護事業所を開業するために必要なステップは下記の4つです。
①法人格を取得する
②事務所と備品を準備する
③人員を確保する
④指定申請を行う
それぞれ解説していきます。
介護保険事業は個人事業主では開業ができないので、訪問介護の事業所を開業するには、法人格を得る必要があります。
法人には主に下表の4つがあります。
| 法人格の種類 | 説明 |
| 株式会社 | 株主から出資を募り、株式を発行して資金を集める法人格 |
| 合同会社 | 経営も利益分配に関しても出資者自身が行う法人格 |
| NPO法人 | 利益が目的ではない社会貢献活動を行う法人団体 |
| 一般社団法人 | 理事1人と社員2人以上が集まれば設立できる非営利法人 |
上記で解説した設備基準を満たすような、事務所や備品を準備する必要があります。
上記でも説明したとおり、訪問介護の事業所を開業するには、訪問介護員、サービス提供責任者、管理者を配置する必要があります。
それぞれの基準を満たせるように、人員を確保しなければなりません。
訪問介護の事業所を開業するためには、指定申請を行い、指定権者からの許可を得る必要があります。
指定権者は都道府県や市区町村ですが、各地域によって異なるので事前に開業する地域のホームページで確認するか直接問い合わせてください。
開業にあたり満たすべき基準をクリアし、期日通りに申請をします。
必要書類や期日も行政のホームページで確認しておいた方がスムーズに行えます。
無事申請が受理されると、6年間の事業が認められます。
訪問介護事業所の開業にかかる主な4つの費用は下記の通りです。
①法人設立費用
②人件費
③施設費
④備品・車両購入費
それぞれ解説していきます。
訪問介護事業所を開業する際に、どの法人スタイルを選ぶかによって、法人設立費用が異なります。
法人設立費用は、
・定款認証手数料
・収入印紙代金
・登録免許税
の3つです。
金額は、株式会社の場合が約30万円、合同会社と一般社団法人の場合が約10万円です。
NPO法人の場合はほぼ費用はかかりませんが、株式会社や合同会社に比べると認可が下りるまでの期間が長く3ヶ月〜4ヶ月ほどかかります。
開業したい時期から逆算して申請をしなければいけない点に注意が必要です。
訪問介護事業所を開業するためには、人員基準を満たしているのが条件であるため、まだ利用者の申し込みがない時点でも人件費を確保する必要があります。
常勤の訪問介護員の月給の相場は18万円〜25万円です。
管理者以外に資格保有者が3人は必要なので、人件費としては最低でも月60万円程必要となります。
さらに、介護保険による介護報酬は、翌月に請求し、翌々月に支払われるので、開業時にはあらかじめ2〜3ヶ月分の人件費を確保しておく必要があります。
訪問介護事業所には、事務作業を行う事務室に加えて、利用者のプライバシーに配慮した相談室と手洗い場が必要です。
そう考えると、6畳ひと部屋の物件では事足りないので、ある程度の広さがある物件を借りることになります。
基準を満たした広さの事務所の賃料と、初めに支払う敷金・礼金も設備費として必要であることを覚えておいてください。
開業資金を抑えるために自宅を事務所として利用するケースもあります。
この場合は賃料・敷金・礼金はかかりませんが、手洗い場などの設備を整えるためのリフォーム資金が必要となる場合があります。
訪問介護事業所では、利用者ごとの訪問計画書を作成したり、介護保険に関する事務作業が発生するので、一般的な事務作業ができる備品を購入する必要があります。
また、相談室用のテーブルや椅子、手洗い場用の衛生用品も備品の一部となります。
具体的には、事務用のデスクと椅子・相談室用のテーブルと椅子・書類保管用のキャビネット(鍵付き)・パソコン・プリンター・FAX・筆記用具・石鹸・消毒液・ペーパータオル等になります。
また、利用者を送迎するための車両も必要ですが、購入する他にレンタルする方法もあります。
車体本体の価格だけでなく、保険料や税金、ガソリン代も開業資金として必要となります。
訪問介護事業を開業する際にかかる費用の詳細は上記の通りですが、自己資金ですべてを賄うことができない方もいるでしょう。
その場合は、助成金や融資を活用することを検討しましょう。
助成金や融資についてそれぞれ解説していきます。
助成金とは、厚生労働省による支援金です。
主に雇用に関しての支援金で、条件を満たしていれば受け取ることができます。
助成金は返済が不要ですし、法令違反があれば申請が受理されないので事業の信用にもつながるといったメリットがあります。
ただし、助成金は申請に必要な実施計画書を作成し、実際に計画書通りに実施した後に申請してから支給されます。
開業時に必要な資金には利用できない場合がほとんどなので、軍資金としては利用できません。
訪問介護事業の開業に活用できる助成金は以下の通りです。
介護労働者の労働条件や職場環境の向上を実現した事業主に対する助成金です。
例えば、労働時間に関する問題・身体的負担の軽減・賃金の処遇といった労働条件の向上や労働者が働きやすい環境を整えることを目的とした費用に対する助成金です。
こちらは雇用管理改善の内容によって以下の2種類の助成金があります。
事業主が新たに機器を導入し、介護労働者の労働環境が改善されたと認められた場合に受けられる助成金です。
まずは「導入・運用計画」を作成して、都道府県の労働局の認定を受けます。
計画期間は3ヶ月〜1年、提出期間は計画開始からさかのぼり6ヶ月前〜1ヶ月前です。
実際に導入した機器を使用した効果については、導入前と導入後に介護労働者に対して行われるアンケートの結果に基づいて査定されます。
無事認定されたら計画期間終了後1ヶ月以内に申請を行います。
支給額は導入費用の1/2(上限300万円)です。
事業主が介護労働者に対する雇用管理改善制度を導入し、労働者の定着や離職率の低下などの効果が認められた場合に受けられる助成金です。
まずは「雇用管理制度整備等管理計画」を作成して、都道府県の労働局の認定を受けます。
計画期間は6ヶ月〜1年、提出期間は計画開始からさかのぼり6ヶ月前〜1ヶ月前です。
雇用管理制度導入日と計画時期間終了時の労働者数の定着率が一定以上であれば助成金の支給が認められます。
認定されたら、計画期間終了後1ヶ月以内に申請を行います。
支給額は導入費用の1/2(上限100万円)です。
参考:厚生労働省
政府出資による金融公庫である「日本政策金融公庫」が行う「新規開業資金」は、事業の創業時や開業して7年以内の若い事業を対象とした融資です。
主に個人事業や小規模事業向けで、実績がなくて他機関からの融資が困難な場合でも低金利での融資が望めます。
融資の限度額は7,200万円、返済期間は、設備資金が20年以内(うち措置期間2年以内)・運転資金が7年以内(うち措置期間2年以内)となっています。
事業計画書や収支計画書など手続きに必要な書類を作成する必要はありますが、無担保・無保証人での融資を希望する場合も相談できますし、他の融資制度との併用できる点は大きなメリットです。
参考:日本政策金融公庫
訪問介護事業所の開業で失敗してしまう理由として、下記の4つが挙げられます。
①資金が不足してしまう
②人材が不足してしまう
③集客力や営業力の不足
④人員・設備・運営基準の理解不足
これらの失敗してしまう理由を理解し、それに対する解決策を立てることで、失敗を避けることが出来ます。
詳しくはこちらの記事で解説しています。
訪問介護の開業で失敗してしまう4つの理由と解決策
少子高齢化により、介護業界の需要は増え、また自宅で自分らしく最期を迎えたいという人が増えたことで、訪問介護の需要は特に増えています。
しかし、需要が増えたことで、競合も増えているため、しっかりと戦略を立てて経営を行わなければ、倒産してしまいます。
訪問介護事業所において、収益を増やす方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
訪問介護の収益モデルはどうなってる?収益を増やすための3つのポイントを紹介!
訪問介護の事業所を開業するためには、基準を理解することはもちろん、法人格を取得したり、開業に必要となる設備や人員の確保、資金の調達など、準備期間として最低でも半年程度は必要となります。
少しずつ必要な準備をすすめて、訪問介護事業所の開業を目指しましょう。