
日常生活継続加算は、認知症や重度の要介護者を受け入れた介護老人施設で算定できる加算です。
また、日常生活継続加算では、テクノロジーを用いた場合、介護福祉士の人員配置要件を緩和させることが可能です。
この記事では2024年度の介護報酬改定で改正された内容や算定要件や最新の情報について、詳しく解説をしています。
初めて日常生活継続加算を算定される事業所の方はぜひ参考にしてみてください。
目次
日常生活継続支援加算とは、認知症の利用者や要介護者などを受け入れた特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設)が算定できる加算です。
日常生活継続支援加算とは、自宅での生活が困難な高齢者の受け入れを促進するために作られました。
公益社団法人全国老人福祉施設協議会が令和4年4月に実施した調査によると、算定率は非常に高く約79%でした。
加算を取得するには、介護福祉士の配置要件を満たす必要があります。加算を取得する事業者は算定要件をよく調べておくことが大切です。
日常生活継続支援加算は2種類あり、それぞれ算定要件が違います。
下記では種類と算定要件についてまとめています。
加算種類 | 算定要件 |
日常生活継続支援加算Ⅰ | ①介護福祉士の配置要件:入所6に対して常勤加算で1以上の人数を配置すること。ただしICT機器などテクノロジーを活用する場合は入所者7に対して1以上の人数を配置すること。 ②次の3つの条件を満たすこと。
③定員超過利用・人員基準欠如に該当しないこと。 ④サービス提供体制強化加算を算定していないこと。 ⑤介護福祉施設サービス費、小規模介護福祉施設サービス費、小規模旧措置入所者介護福祉サービス費、旧措置入所者介護福祉サービス費のいずれかを算定していること。 |
日常生活継続支援加算Ⅱ | 上記1〜4を満たしていること。かつ、ユニット型介護福祉施設サービス費、または超過的ユニット型小規模介護福祉施設サービス費を算定していること。 |
介護福祉士の配置要件については、入所者が6人の場合は常勤換算で1人以上の人数を配置することが必要です。
しかし、ICT機器やテクノロジーを活用する場合は入所者7人に対して1人以上の介護福祉士を配置することが必要です。
入所者の重症度は要介護が4〜5の入居者が70%いることが条件になります。
他にも入居者の総数のうち、認知症日常生活自立度ランクⅢ以上の入所者が65%以上、痰吸引が必要な入居者が15%以上が必要な条件とされています。
認知症の日常生活自立度にはランクがあり、症状もそれぞれ違います。下記では詳しく表にまとめています。
ランク | 判断基準 | 症状・行動 |
Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的に自立している。 | |
Ⅱ | 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても誰かが注意してくれていれば自立できる。 | |
Ⅱ a | 家庭外で上記Ⅱの状態が見られる。 | 度々道に迷うなど、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ。 |
Ⅱ b | 家庭内で上記Ⅱの状態が見られる。 | 服薬管理ができない、電話の対応や訪問者との対応など一人で留守番ができない。 |
Ⅲ | 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 | |
Ⅲ a | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | 着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。 やたら物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、日の不始末、性的異常行為。 |
Ⅲ b | 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | ランクⅢ aに同じ。 |
Ⅳ | 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、常に介護を必要とする。 | ランクⅢに同じ。 |
M | 著しい精神障害や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷、他害等の精神症状に起因する問題行動が継続する状態等。 |
「痰の吸引等の行為」とは、具体的に口腔内や鼻腔内、気管カニューレ内部で痰の吸引を行う行為、胃ろうや腸ろうによる経管栄養などを指します。
上記のケアは医師の指示のもと、施設の介護職員もしくは看護職員から提供されている入所者が該当します。
定員超過については、市に届出の必要はありません。正しく減算していない場合や定員超過利用が2ヶ月以上継続した場合は、指定取り消し等の処分を受けることがあります。
人員の欠如については届出の必要があります。届出がない場合や人員欠如を継続した場合は、指定取り消し等の処分を受けることがあります。
サービス提供加算は事業所内の介護福祉士の資格を保有している人員の割合や勤続年数から事業所を評価する加算です。
日常生活加算は高齢者の入居者を促進するための加算になり、サービス提供体制加算とは同時に算定することはできません。
加算Ⅰは従来型多床室の特養、加算Ⅱはユニット型の特養が対象になります。
下記は認知症の利用者や要介護者など該当する入所者だけでなく、入所者全員に対して算定ができます。
対象事業者 | 単位数(1日あたり) | |
介護老人福祉施設 | 日常生活継続支援加算Ⅰ | 従来型:36単位 |
日常生活継続支援加算Ⅱ | ユニット型:46単位 | |
地域密着型介護老人福祉施設 | 日常生活継続支援加算Ⅰ | 従来型:36単位 |
日常生活継続支援加算Ⅱ | ユニット型:46単位 | |
テクノロジーの活用をすることで人員、運営基準の緩和を通じた業務効率化、業務負担軽減を目的に推進されている。
以下で詳しく解説していきます。
テクノロジーを導入後、利用者に対するケアのアセスメント評価や人事体制の見直しをPDCAサイクルによって継続して行う場合は、当該加算の介護福祉士の配置要件が緩和させることができます。
テクノロジーの種類は4つあります。
主に見守り機器、インカム、記録ソフト等のICT、移乗支援機器が用いられます。
以下の6つが具体的な安全確保の要件になります。
介護現場でのICT導入については、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。
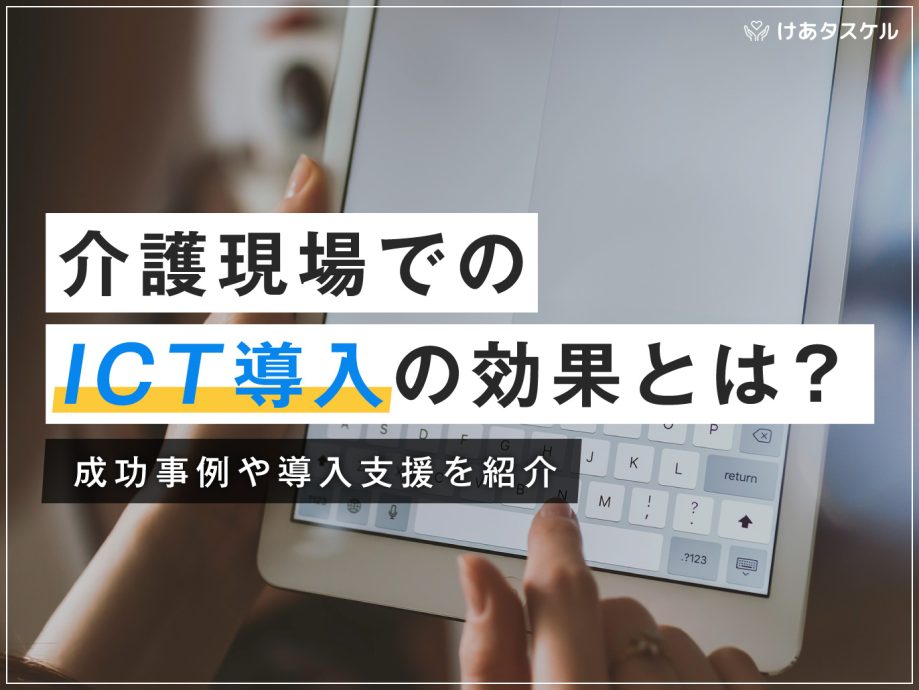
介護現場でのICT導入の効果とは? 成功事例や導入支援を紹介
日常生活継続支援加算の介護福祉士の人数を割り出すには、入所者の平均を計算する必要があります。対象となるのは、届出を出す月の前年度の入所者です。
具体的な計算方法は以下を参考にしてみてください。
前年度の平均入所者数=前年度の入所者(延数)÷前年度の日数
上記の割り出した数値から、次の数式で必要な介護福祉士数を割り出します。
必要な介護福祉士の人数=前年度の平均入所者数÷6
※7:1の要件の場合は7で行います。
以下では、日常生活活動継続支援加算を算定するのに必要とされる書類と提出期限について、解説をしていきます。
これから提出の準備をされる方は、ぜひ参考にしてみてください。
日常生活継続支援加算算定の必要書類は以下になります。
ICTを導入する場合は以下の届出が必要になります。
加算を算定する月の前月15日までが提出期限になります。
ただし、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算については加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があります。
短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、施設サービスは加算を算定する月の初日までに受理されることが必要です。
加算の要件を満たさなくなった場合は、上記日時に関わりなく速やかに提出する必要があります。
併設型のショートステイと兼務している職員に関しては、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により、職員の常勤換算数を本体施設とショートステイそれぞれに割り振った上で、本体施設での勤務に係る部分のみを加算算定のための計算対象にします。
その際、実態としての本体施設と併設のショートステイにおける勤務時間が、1:1程度の割合で兼務している介護福祉士を本体施設のみにおいてカウントするなど、勤務実態と著しく乖離した処理を行うことは認められません。
空床利用型のショートステイにおいては、ショートステイに係る業務を本体施設における業務と分離して考えることは困難であるため、特に按分を行わず、本体施設に勤務する職員として数えても差し支えありません。
算定可能です。
併設型ショートステイについては本体施設と兼務する職員について、勤務実態、利用者数、ベッド数等に基づき按分するなどの方法により、当該職員の常勤換算を本体施設とショートステイそれぞれに割り振った上で、ショートステイに係る職員についてサービス提供体制強化加算の算定基準を満たす場合等は加算対象になります。
他にも空床利用型のショートステイについては、本体施設がサービス提供体制強化加算の算定要件を満たす場合にも算定できます。
入院中も引き続き、退院後の円滑な再入所のためにベッドの確保等を行い、居住費等を徴収されていた者については、新規入所者には含めません。
入所時点での要介護度や日常生活自立度を用います。
日常生活継続加算は要介護の利用者を自施設に迎え入れた際に算定される加算になります。
算定要件の中には介護福祉士の人員配置が求められますが、十分な人員配置は利用者にとっても介護士にとっても良い環境と言えます。
またテクノロジーを導入することで、人員配置も緩和させることも可能になりました。
インカムや見守り機器を導入することで一歩先の介護環境を作ることもできるので、気になる事業所は併せて検討してみるのもオススメです。