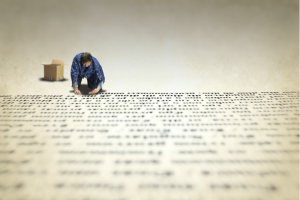本記事では、障害者総合支援法における特定事業所加算について、介護保険法との違いを交えてご紹介いたします。
居宅介護における特定事業所加算の要件

「特定事業所加算」とは、介護保険法と同じく障害程度区分の高い利用者や、支援が困難な場合においても、質の高い介護サービスを積極的に提供し、厳しい算定条件を満たす運用を実施している事業所に対して支払われる加算です。
居宅介護における加算の種類と加算割合は以下の通りです。
特定事業所加算Ⅰ:ご利用者の総単位数プラス20%
特定事業所加算Ⅱ:ご利用者の総単位数プラス10%
特定事業所加算Ⅲ:ご利用者の総単位数プラス10%
特定事業所加算Ⅳ:ご利用者の総単位数プラス5%
人材要件
①
- 介護福祉士の割合が30%以上であること、または介護福祉士+実務者研修修了者(または介護職員基礎研修者、ヘルパー1級修了者)の職員の割合が50%以上従事していること。
- 全てのサービス提供責任者が以下のいずれかを満たしていること。
実務経験3年以上の介護福祉士であること、または実務経験5年以上の実務者研修修了者が従事していること。
- 前年度若しくは算定日が属する月の前3月間におけるサービス提供時間のうち、常勤の従業者によるサービス提供時間の占める割合が40%以上であること。
②
- すべてのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士、又は5年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員基礎研修修了者若しくは1級課程修了者であること。
- 1人を超えるサービス提供責任者を配置することとされている事業所にあっては、常勤のサービス提供責任者を2名以上配置していること。
重度者等対応要件
前年度又は算定日が属する月の前3月間における指定居宅介護の利用者(障害児を除く)の総数のうち、障害支援区分5以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が30%以上であること。
体制要件
- 介護職員に対する計画的な研修の実施
職員すべての個別の研修計画を策定し、実施していることが求められます。
- 定期的な会議の開催
利用者に関する情報やサービス提供にあたっての留意事項の伝達等、介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催します。登録ヘルパーを含めた、すべての介護従事者が参加する会議を開催することが必要です。
- 文書等による指示及びサービス提供後の報告
サービス提供の責任者が利用者を担当する介護員等に対して、利用者に関する情報・サービス提供にあたっての留意事項を文書等で伝達してから開始します。
またサービス提供終了後、担当の介護員等からの適宜報告を受ける事も求められます。
- 定期的な健康診断の実施
事業主費用負担により、少なくとも1年以内ごとに登録ヘルパーも含めた全職員に、1回は実施しなくてはいけません。
- 緊急時等における対応方法の明示
緊急時等における対応方針、緊急時の連絡先及び対応可能時間帯等を記載した文書(重要事項説明書等)を利用者に交付し、説明を行う必要があります。
- 熟練した従業者による新任者同行研修の実施
新規に採用したすべての従業者に対し、熟練した従業者の同行による研修を実施していること。
加算別取得条件
特定事業所加算Ⅰ:体制要件①~⑥、人材要件、重度者要件すべてに適合すること
特定事業所加算Ⅱ:体制要件①~⑥、人材要件①②のいずれかに適合すること
特定事業所加算Ⅲ:体制要件①~⑥、重度者要件に適合すること
特定事業所加算Ⅳ:体制要件②~⑥、以下『加算IVについて』のすべてに適合すること
加算Ⅳについて
- 事業所の全てのサービス提供責任者に対する計画的な研修を実施していることが求められます。
- 常勤のサービス提供責任者が二人以下の介護事業所であり、その事業所に配置されるべきサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ基準の配置人数より1人以上多いサービス提供責任者を配置している事が条件です。
- 前年度又は算定日が属する月の前3月間における指定居宅介護の利用者(障害児を除く)の総数のうち、障害支援区分4以上である者及び喀痰吸引等を必要とする者の占める割合が50%以上であること。
介護保険法との違い

介護保険法との大きな違いは、体制要件の中の『熟練した従業員による新任者への同行研修実施』です。
新規に採用し、勤務形態一覧表に氏名があがる従業員はすべて同行研修を実施しなければいけません。
ここで言う『熟練した従業員』とは、サービス提供責任者又はサービス提供責任者と同等と認められる従業者(当該利用者の障害特性を理解し、適切な介護を提供できる者であり、かつ、当該利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある従業者)とされています。
また、同行研修の回数は問われていませんが、同行による研修を実施した場合、提供記録の備考欄等に同行者の氏名、同行した時間、研修内容を記録しなければいけません。
特定事業所加算の申請時には、直近3か月~1年以内に新規に採用した従業者の同行研修記録が求められる場合があり、新規に採用した従業者がいない場合は、同行による研修体制が整っていることを証する書面が求められます。
(申請時に必要な書類、期間は自治体によって異なります)
届出を行った月以降においても、毎月、新規に採用した全てのヘルパーに対して当該研修を実施している必要がありますので、継続して同行研修を行う体制を整える必要があります。
さいごに
居宅介護の特定事業所加算は、介護保険法における訪問介護の特定事業所加算とほぼ同じ要件であり、訪問介護事業所と居宅介護事業所を併設している事業所の多くは、両方特定事業所加算の取得をされている場合が多いのが実情です。