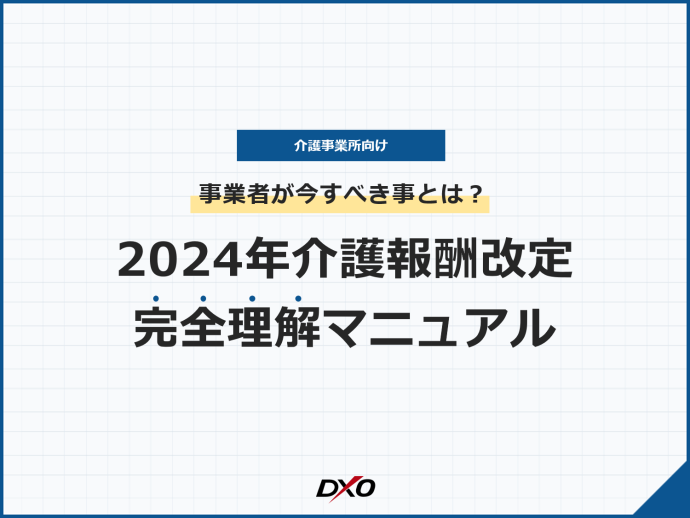この記事では、2040年に向けて介護業界がどのように変化していくのかをご紹介していきます。

これまで、国や自治体は2025年に向けて介護保険の設計をし、加算などを用いて介護事業所を国が目指す方向へと導いてきました。
2025年は、1947年~1949年の第一次ベビーブームで生まれた「団塊世代」が75歳となる年で、消費税の10%への増税は、2025年問題への対策である「社会保障、税一体改革」のために実施されたものです。
2040年になると、1971年~1974年の第二次ベビーブームに生まれた「団塊ジュニア世代」が65歳〜70歳となり、これまで以上に労働人口が減る為、今はこの2040年に向けた施策が取られ始めています。
日本全体で2018年に6580万人であった労働人口は、2040年には5650万人までに減る中で、介護業界に人が流れてくることは考えにくい状況です。
2000年にはじまった介護保険ですが、当初3.6兆円だった介護給付費が2025年には21兆円にまで膨れ上がる予定です。
介護給付費が増え続けることは制度当初から想定されており、これまで特別養護老人ホーム入所対象者を要介護3以上に絞る、介護予防給付を総合支援事業へ移行させる等、介護給付費の対象となる給付の母数を減らしてきた背景があります。
2024年度以降の分母を減らす対象は、令和4年現在介護給付費の割合の43%を超える『居宅系サービス』となっています。

国全体の課題に対した施策において、介護に求められているのは【医療・福祉サービス改革プラン】として2040年時点で、単位時間当たりのサービス提供を5%(医師は7%)以上改善することです。
このために以下の4つのアプローチにより、取組を推進していくとの方針がかかげられています。
・ロボット・AI・ICT等の実用化推進、データヘルス改革
・タスクシフティングを担う人材の育成、シニア人材の活用推進
・組織マネジメント改革
・経営の大規模化・協働化
2040年までの改定には、この方針の中で改定がかかっていくことが予想されています。

運営をしていくにあたっての介護報酬改定における考え方のポイントは以下3点です。
①介護給付費の対象となる分母が減っていく
膨れ上がる介護サービスの給付に対し、対象となる分母を減らしていくことが考えられています。
これまで特別養護老人ホームが要介護3以上のみ対象となることや、介護予防給付がなくなり総合事業になること等、居宅系サービス以外を対象にしてきましたが、今後は居宅系サービスに対して分母を減らしていく取り組みが行われていきます。
②介護給付費のご利用者様負担が増える
医療では2022年に2割負担の対象となる人数が増えることが決定しており、これに追随するように介護が続くとみられています。
また、令和3年度の介護報酬改定で見送られたケアプランの自己負担額の導入等についても検討導入が続いていく方向です。
③民間サービスの多様化
介護給付の対象となる人数を絞ることであふれ出たご利用者様は、『専門知識を有する介護職員からの介護支援は必要ない』という判断のもと、民間サービスを使用していくこととなります。
例えば買い物の支援は『移動販売』『宅配サービス』等、掃除は『ボランティア』『家政婦』等、調理は『作りおき宅配』等、現在は老人だけを対象とせず、家庭生活を支援するサービスが充実してきており、これまで『人が作ったものでなければ食べられない』『お茶を外で買うなんてばからしい』といった世代の方達を対象としていたものが、これからは『冷凍食品』『コンビニ』に慣れた方が対象となって来るということも特徴です。

2024年の報酬改定に向けて、議論が進んでいる中、『要介護1,2が総合事業へ』『生活援助が介護給付からなくなる』等、軽度者が訪問介護の対象外とされる議論が過熱しています。
このような中、加算の取得を行い、医療依存度の高いご利用者に対応できる体制を整えることは非常に重要です。