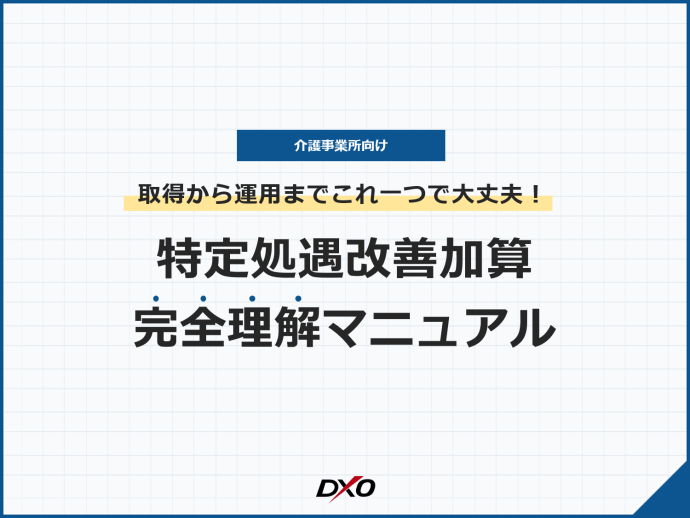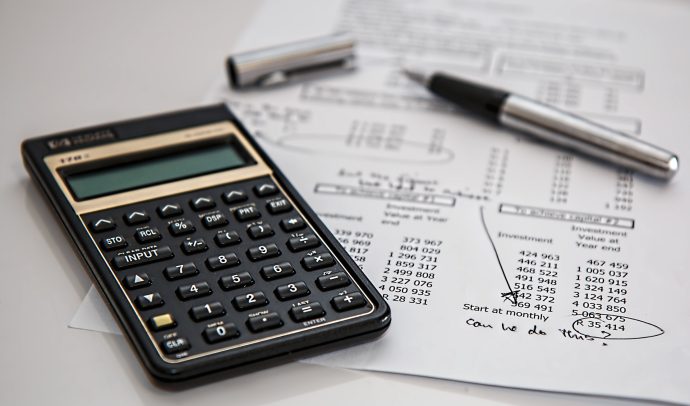
特定処遇改善加算とは、介護職員の処遇改善を目的とした加算のことを指します。ただし、2024年度の介護報酬改定にて見直しが予定されており、今後どのように扱われるか気になっている方も多いのではないでしょうか。
今回は、特定処遇改善加算の概要と施設管理者が知っておくべきルールについて解説します。この記事を読むことで、算定に必要な条件や注意事項が理解できるでしょう。ぜひ最後までお読みください。
目次
特定処遇改善加算は2024年度の介護報酬改定にて、処遇改善加算・ベースアップ等支援加算との一本化が行われる見通しです。一本化後の処遇改善加算については以下の記事で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。
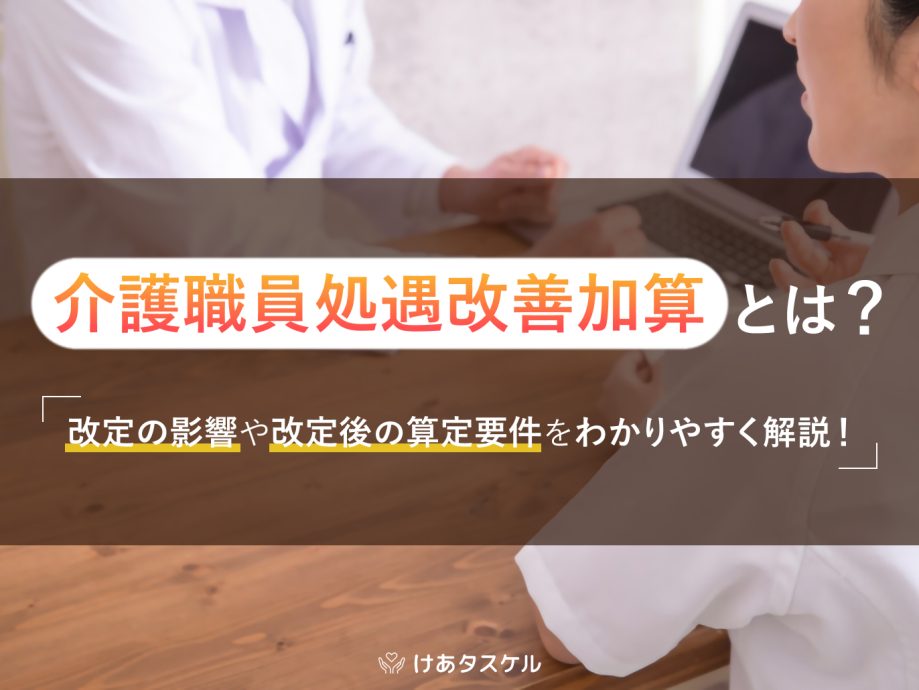
【2024年改定対応】介護職員等処遇改善加算とは?改定の影響や改定後の算定要件をわかりやすく解説!
なお、本記事では2023年度まで用いられていた特定処遇改善加算について解説します。
特定処遇改善加算とは「経験・技能のある介護職員」について、今までの介護職員処遇改善加算に加え、さらなる処遇改善を進めるための加算として、令和元年10月の介護報酬改定により創設された制度です。
介護の現場は、深刻な人手不足が問題となっています。
介護労働安定センターが行った実態調査からも、介護サービス事業を運営するうえでの問題点として「良質な人材の確保が難しい」が49.8%と最も多く、次いで「今の介護報酬では、人材の確保・定着のために十分な賃金を払えない」が39.8%となっています。退職の理由のトップは職場の人間関係ですが「収入が少ない」と回答する者も一定数(14.9%)いるようです。
そのため、介護の現場で長く働く経験豊富な介護職員の処遇を改善し、介護の労働環境をよりよくして介護離職を防ぐことが課題となっています。特定処遇改善加算が創設されるに至った背景には、慢性的な人手不足を解消し優秀な介護人材を確保する取り組みを、より一層すすめる狙いがあるのです。
特定処遇改善加算は次の要件を満たせば、加算を取得できます。
特定処遇改善加算は、既存の処遇改善加算に上乗せする形で加算されます。そのため、特定処遇改善加算を算定するためには、現行の介護職員処遇改善加算(I)〜(Ⅲ)の算定が条件になります。
職場環境等要件として、賃金以外の職場環境改善の取り組みを行わなくてはなりません。例えば、研修の実施などキャリアアップに向けた取り組みや、ICTの活用などの生産性向上の取り組みなどが要件です。
特定処遇改善加算に基づく取り組みの見える化については、介護サービス情報公表性度を利用して、以下の内容の公表が求められています。
ただし、介護サービス情報公表制度以外にも、ホームページを用いて情報を公表・公開することで代用できます。
処遇改善加算を算定するためには、職場環境等要件を満たさなければなりません。
職場環境等要件は、以下の表を参考にしてください。
職場環境等要件の区分 | 具体的内容 |
入職促進に向けた取り組み |
|
資質の向上やキャリアアップに向けた支援 |
|
両立支援・多様な働き方の推進 |
|
腰痛を含む心身の健康管理 |
|
生産性向上のための業務改善の取り組み |
|
やりがい・働きがいの醸成 |
|
特定処遇改善加算では、上記表の6つの区分すべてにおいて、それぞれ1つ以上取り組まなければなりません。また、計画期間中に実施する上記表にある取り組みについては、その内容の全職員への周知も求められています。
特定処遇改善加算は、経験・技能のある勤続年数の長い介護職員の処遇改善が目的です。「経験・技能のある介護職員」とは、勤続10年以上の介護福祉士が基本となります。
しかし「勤続10年」の判断基準は、事業所の裁量に任されています。他の法人での勤務期間も含めることや、医療機関での経験等を加味することも可能です。また「勤続10年」には満たずとも、その事業所独自の判断基準に基づいて加算算定の基準とすることも認められています。
特定処遇改善加算の計算方法は、現行の処遇改善加算と同様です。
「各事業所の介護報酬」×「各サービスの特定加算(Ⅰ)または(Ⅱ)の加算率」=「加算による収入」
特定処遇改善加算は、1ヵ月分の基本報酬から、処遇改善加算分を除いた加算・減算を足し引きした単位数に、加算率を掛けることで算定できます。
特定処遇改善加算の加算率は、取得している加算の種類や提供しているサービスによって変わります。
詳しい内容は、下記の表を参考にしてください。
サービス区分 | 特定処遇改善加算 | |
加算Ⅰ | 加算Ⅱ | |
訪問介護・夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 6.3% | 4.2% |
(介護予防)訪問入浴介護 | 2.1% | 1.5% |
通所介護・地域密着型通所介護 | 1.2% | 1.0% |
(介護予防)通所リハビリテーション | 2.0% | 1.7% |
(介護予防)特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護 | 1.8% | 1.2% |
(介護予防)認知症対応型通所介護 | 3.1% | 2.4% |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護 | 1.5% | 1.2% |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 3.1% | 2.3% |
介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・(介護予防)短期入所生活介護 | 2.7% | 2.3% |
介護老人保健施設・(介護予防)短期入所療養介護(老健) | 2.1% | 1.7% |
介護療養型医療施設・(介護予防)短期入所療養介護(病院等) | 1.5% | 1.1% |
介護医療院・(介護予防)短期入所療養介護(医療院) | 1.5% | 1.1% |
加算の割合は、加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の2つの区分があります。
加算(Ⅰ)は、サービス提供体制強化加算の最も上位の区分を算定している場合に、算定が可能です。それ以外は、加算(Ⅱ)となります。
特定処遇改善加算の対象となる職員は、以下の3種類に分けられます。
「A:経験・技能のある介護職員」とは、基本的に勤続10年以上の介護福祉士となります。勤続年数は、他の法人や医療機関などの経験も通算可能です。また10年の経験が無くても、事業所の能力評価基準などに基づき、対象にできます。
配分のルールは、以下のようになっています。
ただし、次の場合は、月額8万円の賃上げもしくは年収440万円の賃金増の条件を満たさなくても、算定できます。
特定処遇改善加算は、対象の職員や配分ルールなどが、事業者の裁量に任されています。そのため、各事業所の事情により柔軟な対応ができる反面、基準に則っているかわからず判断が難しい場面も多くあるようです。ここでは、特に判断が難しい部分をQ&Aで解説します。
加算申請以前に年額440万円以上の者がいる場合は、「月額平均8万円以上」または「年額440万円以上」のものを新たに1人以上確保する必要はなく、現状で加算の算定が可能となります。
「経験・技能のある介護職員」について「月額8万円以上」もしくは「年収440万円以上」の設定・確保が難しい場合、特定処遇改善加算の計画書に3種類の理由が記載された項目があります。
該当する項目にチェックを付けて届け出してください。
特定処遇改善加算対象者の雇用形態については、特に明記されていません。したがって、基本的に非常勤職員も含まれます。
当加算の算定対象サービス事業所における業務についている場合は、その他の職種に含められます。具体的には労使の合意のもとで、法人・事業所の判断となります。
特定処遇改善加算は、事業所に判断が任されるなど、とまどう部分も多数あります。しかし算定自体はそれほどハードルが高い物ではありません。介護職員の処遇改善のため、しっかりと算定要件等を理解し加算の算定を検討しましょう。