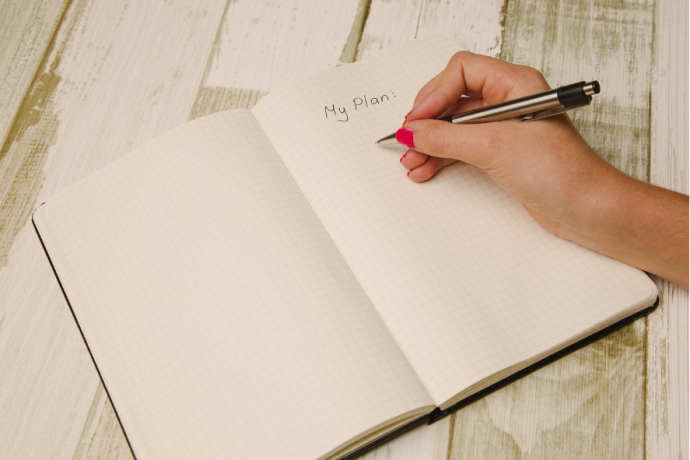
特定事業所加算を算定するためには、いくつかの要件をクリアしなければなりません。その中でも特に重要なのが、職員のスキル向上を目的とした研修をおこなうために作成する「個別研修計画」です。
この個別研修計画では、事業所に勤務するそれぞれの職員について、具体的な研修目標や研修内容、研修時期、実施期間などを定め、最低でも年に1回以上の研修を実施することが求められています。
個別研修計画とは、職員一人ひとりに対してどのような研修を実施するかを明確に示すものです。例えば、介護職員のうち新人には基礎的な介護技術の習得を目指した研修を実施し、経験豊富な職員には、そのスキルをさらに深める専門的な研修を実施します。
また、研修の進捗や目標達成状況を定期的に確認し、必要に応じて計画を見直すことで、職員の成長をサポートしていきます。個別研修計画を適切に策定することで、職員一人ひとりの成長を促し、事業所全体のサービス向上を図ることができます。
そのため、個別研修計画を作成する方針は、職員一人ひとりの能力や経験に合わせた具体的な内容を設定することです。個人のニーズや事業所の方針を明確にし、継続的なステップアップを図れるようにする必要があります。
\ この記事を読んでる方に おすすめの資料 /
個別研修計画は、職員一人ひとりのキャリアや役割、現状のスキルに応じた成長支援を目的に作成されます。厚労省の定める研修義務(介護職員等特定処遇改善加算など)への対応にもなり、処遇加算を取得・継続するための要件としても重要です。
作成時のポイントは以下のとおりです:
- 本人のキャリア意向を反映すること(ヒアリングが必須)
- 現場で必要とされるスキルや知識を具体的に反映
- 施設の研修方針や評価制度と連動させる
事業所の実情や業務内容を考慮しながら、形だけではない“実効性のある計画”を目指しましょう。
| 項目 | 内容の例 |
| 氏名 | 対象職員の氏名 |
| 現在の職位・職種 | 介護職員(常勤)・パートなど |
| 勤続年数 | 例:3年4ヶ月 |
| 現在のスキル | 基本的な介助は可能。リーダー業務は未経験など |
| 課題・目標 | 排泄介助の質向上、認知症ケアの理解など |
| 実施する研修内容 | 外部研修:認知症対応研修 内部研修:記録の書き方 |
| 研修の時期・頻度 | 6月:外部研修参加 8月:内部OJTなど |
| 評価・振り返り方法 | 上司との面談、自己評価シートの提出など |
※これらを1人ずつ作成することで、処遇改善加算・特定処遇改善加算に必要な「資質向上の取り組み」として証明できます。
\ この記事を読んでる方に おすすめの資料 /
| 時期 | 内容 |
| 4月 | 新年度方針に沿って「研修テーマの決定」「計画フォーマットの見直し」 |
| 5月 | 全職員へのヒアリング(目標や希望研修の確認) |
| 6月 | 個別研修計画を作成・共有、必要に応じて修正 |
| 7月〜2月 | 計画に基づき研修実施、記録・評価を随時おこなう |
| 3月 | 年度末面談で振り返り、次年度の課題整理へ |
職員の意欲と納得感を引き出すためにも、ただの「提出書類」ではなく、育成と定着につながる機会として活用することが重要です。
以下は介護職員(入職3年目)の記入例です。
| 項目 | 内容 |
| 氏名 | 田中 花子 |
| 現在の職種 | 介護福祉士(常勤) |
| 現在のスキル | 入浴・排泄・食事介助は一通り対応可能。認知症利用者への対応に不安がある。 |
| 課題・目標 | 認知症利用者への関わり方を深め・ケアマネとの連携経験も積みたい。 |
| 実施予定の研修 | 認知症ケア研修(7月受講)・OJT(ケース記録の指導、10月) |
| 評価方法 | 面談(年2回)・記録の添削チェック表 |
\ この記事を読んでる方に おすすめの資料 /
個別研修計画は加算要件としても重要であり、職員の定着・育成にも直結します。
本人のキャリア意向を反映しつつ、施設の目標と連動した計画を立てることがポイントです。
年度スケジュールをもとに、事前準備から振り返りまで一貫して進めることで形骸化を防げます。加算対応のためだけでなく、職員との対話を深めるツールとして活用していきましょう。
