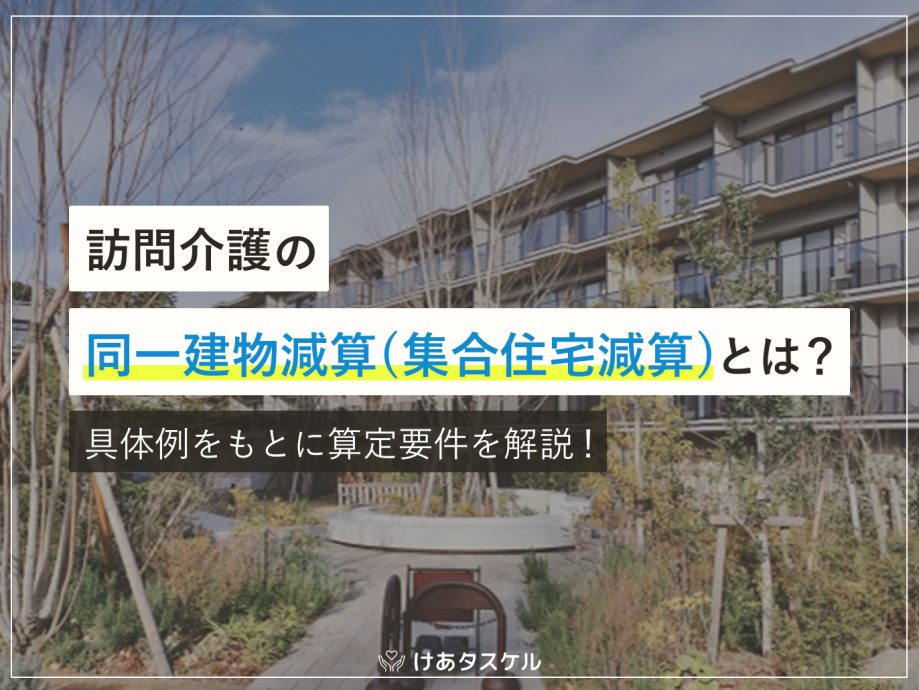
同一建物減算(集合住宅減算)とは、介護保険給付の公平性を確保する観点から、事業所と同一建物に居住する利用者へのサービス提供が効率的にできることを理由におこなわれる減算です。ただし、同一建物減算は算定要件が複雑で2024年の介護報酬改定でも見直しが予定されていることから、あまり詳しく理解できていなかったという人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では訪問介護サービスにおける同一建物減算について詳しく解説をおこないます。算定要件や減算率についてはもちろんのこと、2024年の介護報酬改定に伴う変更点についても詳しく解説するので是非参考にしてください。
目次
2024年の介護報酬改定では訪問介護の同一建物減算に見直しがおこなわれる予定です。見直しがおこなわれた背景としては、集合住宅の利用者を集中的に囲い込む一部の訪問介護事業者に対して「公平性に欠ける」との声が現場の関係者からあがったことがあげられます。
実際に厚生労働省が発表している「令和5年度介護事業経営実態調査」でも、同一建物にサービス提供をおこなう事業所について指摘がおこなわれており、同一建物減算が算定されていない(同一建物でのサービス提供をおこなっていない)事業所の収支率が6.7%だったのに対し、同一建物減算が算定されている(同一建物でのサービス提供をおこなっている)事業所の収支率が9.9%と比較的高いことがわかります。
2024年の介護報酬改定における同一建物減算の変更点は、12%の減算区分が新設されることです。従来の算定要件では、サービス提供をおこなう事業所と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する建物に居住する利用者の人数が50人以上の場合は15%の減算、それ以外の場合は10%の減算とされていました。ただし、2024年の介護報酬改定にて、利用者数が50人未満の場合でも、サービス提供をおこなっている利用者のうち9割以上が事業所と同一の建物に居住している場合は12%の減算が適用される予定です。
なお、2024年の介護報酬改定の全容について把握したい方は、あわせて以下の記事も参考にしてください。

【2024年介護報酬改定】改定ポイントまとめ|最新情報を元に一覧で徹底解説
同一建物減算(集合住宅減算)とは、事業所と同一建物に居住する利用者へサービス提供をおこなう事業所を適切に評価するための減算です。
通常の訪問介護事業の場合、訪問介護員が利用者の自宅を訪問しサービス提供をおこなうため、訪問介護員が移動をおこなう時間が発生します。その一方で、訪問介護事業者と利用者が居住する建物が同じだった場合、訪問介護員が移動をおこなう時間を大きく減らすことが可能であり、業務効率に大きな差が生まれることが容易に予想されます。
上記の背景から、サービス提供に対する報酬を適切に評価することを目的に同一建物減算が導入されています。
以下で紹介する減算率や算定要件は、2024年4月1日施行予定の介護報酬改定による変更点を反映したものになります。
現行の算定要件と異なる場合がございますのでご注意ください。
また2024年4月1日の介護報酬改定に伴う変更点は赤字で記載を行っています。
訪問介護の同一建物減算における算定要件と減算率は以下の通りです。
| 減算の内容 | 算定要件 |
| 1. 10%減算 | 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(2および4に該当する場合を除く) |
| 2. 15%減算 | 上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1ヵ月あたり50人以上の場合 |
| 3. 10%減算 | 上記1以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1ヵ月あたり20人以上の場合) |
| 4. 12%減算 | 正当な理由なく、事業所において、前6ヵ月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(2に該当する場合を除く)に提供されたものの占める割合が90%以上である場合 |
算定要件のみではやや理解が難しいため、具体例とともにどのように減算されるかみていきましょう。
具体例1では以下の状況にある訪問介護事業所を例に減算を計算していきます。
このような状況の場合、まず「事業所と同一の建物に居住する19人の利用者」については算定要件1より10%減算の対象となります。また「それぞれの住宅にてサービスを利用する11人の利用者」は同一建物に居住していないため減算の対象外です。
具体例2では以下の状況にある訪問介護事業所を例に減算を計算していきます。
このような状況の場合、まず「事業所と同一の建物に居住する30人の利用者」については算定要件1より10%減算の対象となります。また「同一の集合住宅にてサービスを利用する20人の利用者」も算定要件3より10%の減算となります。
具体例3では以下の状況にある訪問介護事業所を例に減算を計算していきます。
このような状況の場合、まず「事業所と同一の建物に居住する50人の利用者」については人数が50人を上回っているため算定要件2より15%減算の対象となります。ただし「それぞれの住宅にてサービスを利用する50人の利用者」は同一建物に居住していないため減算の対象外です。
具体例4では以下の状況にある訪問介護事業所を例に減算を計算していきます。
このような状況の場合、まず「事業所と同一の建物に居住する49人の利用者」については、人数が50人を下回っているため算定要件1より10%減算が適用されるように考えられます。ただし、2024年に施行される介護報酬改定にて全体の利用者数のうち同一建物に居住する利用者が90%を超える場合は12%の減算が適用されるため、12%の減算となります。
なお「それぞれの住宅にてサービスを利用する1人の利用者」は同一建物に居住していないため減算の対象外です。
算定要件に記されている「同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物」には定義が定められています。建物の定義は以下の通りです。
具体的な例としては、利用者が居住している集合住宅の1階に事業所を構えているケースや、同一の敷地にある別棟の建物に事業所を構えているケース、または幅の狭い道路を挟んで事業所を構えているケースなどがあげられます。
一方で、建物自体の定義のほかに「効率的なサービス提供が可能なもの」という条件があるため、敷地が広大で建物間の移動に時間を有するケースや、施設の間に幹線道路や河川を挟んでいるケースなどでは、減算対象とならないこともあります。
最後に同一建物減算に関するよくある質問とその回答を紹介します。
サービス提供をおこなう事業所と利用者の入居する建物の運営法人が異なる場合でも、算定要件さえ満たしてさえいれば同一建物減算の対象になります。
同一建物減算は介護保険給付の公平性を担保することを目的とした施策であり、減算の有無は事業者のサービス提供効率を加味して判断されます。
同一建物減算は介護保険給付の公平性を維持する観点から、同一建物内に事業所をかまえることでサービス提供が効率的におこなえてしまう事業所にあたえられる減算です。
ただし、減算に関する算定要件や同一建物の定義は複雑で理解が難しいため、情報を正しく読み解いて要件を満たしているかを紐解く必要があります。
本記事を参考に訪問介護の同一建物減算を確認する際にお役立てください。