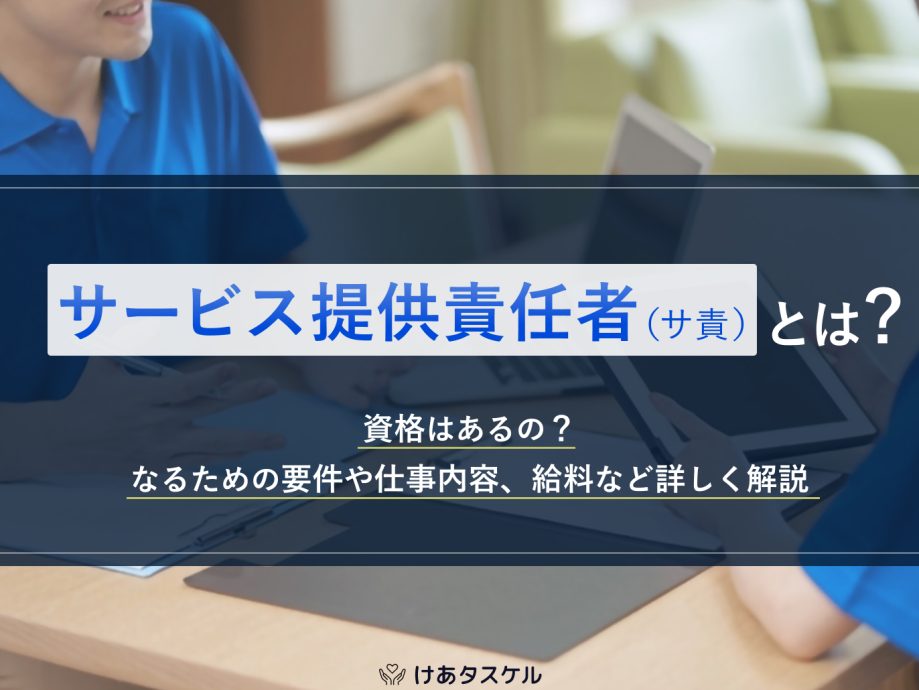
サービス提供責任者とは、訪問介護サービスにおいてケアマネージャーとヘルパーの間に立ち、訪問介護計画の作成やヘルパーの管理をおこなう役割を担った人のことを指します。とはいえ、サービス提供責任者の具体的な仕事内容や、なるために必要な要件については詳しく知らないという人も多いのではないでしょうか。
本記事ではサービス提供責任者とはどのような仕事なのかわかりやすく解説します。サービス提供責任者の仕事内容や、配置基準などについても紹介するのでぜひ参考にしてください。
目次
サービス提供責任者について一言で説明をすると、訪問介護サービスを管理する役割を担った人のことを指します。具体的には、ケアマネージャーが作成したケアプランを基に訪問介護計画書を作成し、現場のヘルパーに指示や指導をおこなうことが主な仕事といえるでしょう。
以下ではより具体的な仕事内容や、働き方がイメージできる一日のスケジュール例を紹介します。
サービス提供責任者の仕事内容は大きく分けると以下の8つとなります。
サービス提供責任者は訪問介護サービスを利用したいと考える方の窓口的な業務を担当します。
訪れた利用希望者もしくはその家族に対して、サービスの利用を開始するにあたって必要な情報をヒアリングし、その後はサービス利用に向けた手続きや事業所内の連携などをおこないます。
アセスメントとは、介護サービスを利用する方の悩みや希望、体の状態や周囲の環境についてヒアリングをおこない、その内容をもとに適切なケアを検討するプロセスのことを指します。
アセスメントから利用者や家族が在宅で生活を継続するために課題となっていることを導き出し、これを解決するための計画を策定していきます。
サービス担当者会議とは、ケアマネージャーが作成したケアプランをもとに、サービス提供をおこなうスタッフに対して、情報の共有や支援内容の検討をおこないます。
複数のサービス事業所が参加しますが、サービス提供責任者は訪問介護の視点でケアプランに位置づけられたサービスが適切かなどを確認していきます。
訪問介護計画書とは、サービス提供責任者が作成する書類のひとつで、訪問介護サービスについて提供をおこなう具体的な内容をまとめたものです。
訪問介護計画書はケアマネージャーが作成したケアプランをもとに作成され、以下の内容を中心に詳細な提供サービスが記載されます。
サービス提供手順書とは、現場で介護実務を担当するヘルパーに向けたサービス提供に関する内容や手順をまとめた資料です。作成は必須ではありませんが、現場のヘルパーたちが作業に悩まず質の高いサービスを提供するための指示書として用いられていることが多くあります。
サービス提供手順書については以下の記事でも解説しているので、あわせてご確認ください。
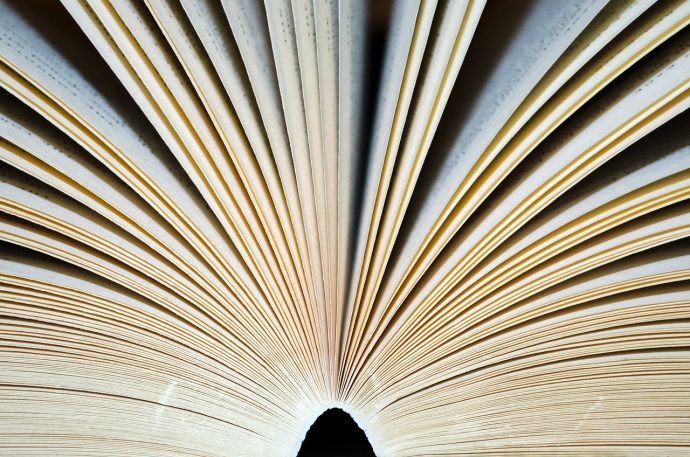
訪問介護における手順書とは?手順書作成におけるポイントと注意点!
初回のサービス提供や、経験が浅いヘルパーがサービス提供をおこなう場合は、サービス提供者が同行し、ヘルパーをサポートします。
また、同行訪問の際にアセスメントやサービス担当者会議で知り得た利用者や家族の状況や、サービス提供にあたって注意すべき事などをヘルパーに伝達することも大切です。
ヘルパーからの業務報告や、定期的な利用者宅への訪問をおこなうことで、利用者の状態や状況についてモニタリングをおこないます。
モニタリングの結果によっては、訪問介護計画書やサービス提供手順書を修正し、よりよいサービス提供をおこなうために尽力します。
その他現場のマネジメント的な観点から、ヘルパーの技術指導や研修計画管理、欠勤時やトラブルへの対応などをおこないます。
サービス提供責任者の一日のスケジュール例は以下となります。ただし、サービス提供責任者の業務は多岐にわたるため、あくまで一例として覚えておきましょう。
| サービス提供責任者のスケジュール例 | |
| 08:30 | 出勤 |
| 09:00 | 訪問介護計画書の作成 |
| 10:30 | その他事務作業 |
| 12:00 | お昼休憩 |
| 13:00 | 利用者宅へ移動 |
| 14:00 | 利用者宅にてモニタリング |
| 15:00 | 関係機関との連携・連絡 |
| 16:00 | 訪問介護業務(ヘルパーの欠勤に伴う対応) |
| 17:00 | ヘルパーへの業務指示・教育 |
| 17:30 | 退勤 |
厚生労働省が公表している「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、正社員の場合のサービス提供責任者の平均的な給料は、月給33万9,000円程度でした。
この金額を年収換算*¹すると、約475万円となります。勤続年数や残業の有無によって変動しますので、あくまで参考値として覚えておきましょう。
*¹:ボーナスを月収2ヵ月分として、月収×14ヵ月分にて試算
サービス提供責任者を目指したい人は以下のポイントを抑えておきましょう。
「サービス提供責任者」という名前の資格や試験が存在するわけではありません。あくまでも役割の名称です。ただし、サービス提供責任者になるには、一定の資格等を保有している必要があります。
これらの資格を持っている方は、サービス提供責任者になることができます。
なお、以前は介護職員初任者研修(旧課程ホームヘルパー2級)のうち実務経験を積んだ人もサービス提供責任者になることができましたが、現在はこの方法でなることはできません。
訪問介護事業所を運営するためには、サービス利用者の数に応じてサービス提供責任者を配置することが義務付けられています。以下ではサービス提供責任者の配置基準について解説します。
訪問介護事業所には、必ず1人以上のサービス提供責任者を置かなければなりません。ただし、何人置かなければならないかは、直近3ヵ月間の利用者数によって異なります。
利用者が40人までは、サービス提供責任者は常勤で1人いれば足ります。その後は41人~80人までは2人、81~120人までは3人と、40人ごとに1人の割合で増加します。
| 直近3ヵ月の利用者数 | 必要なサ責の数 |
| 40人以下 | 1人以上 |
| 41人以上80人以下 | 2人以上 |
| 81人以上120人以下 | 3人以上 |
| 121人以上160人以下 | 4人以上 |
| 161人以上200人以下 | 5人以上 |
なお、常勤で3人以上のサービス提供責任者が確保できている、ヘルパーとして働いた時間が月30時間以内のサービス提供責任者が1名以上いるなど一定の条件を満たした場合は、特例的に50人に対し1人でも認められることがあります。
サービス提供責任者は、必ずしも専任でなくてもかまいません。ヘルパーとの兼任や、事業所の管理者との兼任も認められています。
もっとも、注意が必要な場合もあります。まず、ヘルパー・サービス提供責任者・管理者の3役をすべて兼任することはできません。管理者との兼任は、サービス提供責任者としては問題がなくても、自治体より管理者の要件の面で条件付きの場合があります。
また、同一の事業者が随時訪問介護看護事業や移動支援事業を併設している場合、事業内容や職務内容によって兼務できるかどうかが変わってきます。しかし、併設されているのが有料老人ホームなどの施設である場合は、サービス提供責任者は「専従」が原則であるため、原則として兼務できません。
アルバイトやパートなどの非常勤でもサービス提供責任者になることができます。
ただしヘルパーと違い、非常勤のサービス提供責任者は週20時間以上勤務でなければならないという条件があります。結果として、同じアルバイト・パート勤務でも、ヘルパーより勤務時間も収入も多くなる可能性は高いでしょう。扶養内で働きたい、家庭の事情を優先したいなどの希望がある場合には、よく検討する必要があります。
なお、サービス提供責任者の人員配置基準においては、勤務時間が週20時間の場合カウントは0.5人扱いとなり、担当可能な利用者は20人までとなります。最低を0.5人換算とし、それ以降は勤務時間数によって増加します。
また、最低1人は常勤のサービス提供責任者を置かなければならず、配置基準1人の場合でも非常勤2名で1人とすることは認められません。
さいごにサービス提供責任者についてのよくある質問とその回答を紹介します。
サービス提供責任者には、まず何よりもヘルパー以上の介護技術、知識、経験が求められます。利用希望者やご家族と話す中で相談やアドバイスに発展することもありますし、利用者ごとの短いモニタリングの時間で状態の変化を発見し、必要な計画や指示・手順の変更を把握する能力も必須です。
利用者の状態変化やそれに伴うサービス提供手順の変更について、サービス提供責任者は責任を持ってヘルパーに伝えなければなりません。全体的なケアの見直しが必要なときには、ケアマネージャーとも連絡調整を行い、話し合いをすることもあります。これらのコミュニケーションを行える力が必要です。
また、問題が起きた場合の対応や指導教育も行うことから、事務的な連絡ができる能力だけでなく、ヘルパーと普段から良好な関係を維持できる能力も必要になります。介護の技術・知識やコミュニケーション力は、ヘルパーとしてケアを行う中でも身に着くものです。サービス提供責任者を目指すのであれば、まずはヘルパーとしてのケアに丁寧に取り組んでいくことが、責任者としての能力にもつながります。
しかし、ヘルパーとはまったく異なるスキルもあります。それが「事務処理能力」です。急なお休みをしたヘルパーの代わりを探して調整し、しかもそのことを利用者さんやご家族にも納得していただく調整力、サービス提供手順書や研修計画書などの書類を作ったり整理したりする能力などは、ヘルパーの仕事だけでは身に着けにくいものです。逆にこれらの能力に自信がある場合は、サービス提供責任者にも向いているかもしれません。
サービス提供責任者は重大な職務ですが、やりがいも大きい仕事です。利用者さんにも、利用前から継続して関わりを持つことができます。とくに、ヘルパーの立場では決めることができなかったケアの計画や手順について、自ら決定に関与していくことができる立場になります。
また、モニタリングを通じて、一人一人の利用者さんとも長く、密に関係を築いていくことが可能です。さらに、利用者さんとの関係だけでなく、ヘルパーの成長にも関わり、組織全体も見ていくことができます。もちろん、責任に応じた給料や待遇の向上も望めます。ケアに伴う身体的な負担も、ヘルパーよりは少ない傾向があります。ヘルパーよりも多様な立場の人と会うことが多くなり、視野が広がることも将来を考えていくうえで大きなメリットです。
ケアマネージャーは、利用者がどのような介護サービスを利用するかを検討・調整し、ケアプランを作成します。利用者が利用する介護サービスの全体像に関わるため、利用者と訪問介護事業所との間だけでなく、各種の施設や訪問看護サービスなどとも調整をしています。
これに対しサービス提供責任者は、ケアプランの中に位置付けられた訪問介護事業所の責任者として、ケアマネージャー・ヘルパー・利用者の間での調整を行う役割です。
サービス提供責任者としての業務では、夜勤はありません。
ただし、サービス提供責任者がヘルパーと兼任している場合、夜間対応型の事業所であれば、ヘルパーとしての夜勤はありえます。
現場の介護技術だけではないマネジメント力や処理能力が身に着くところから、事業所の管理者やケアマネージャーになる人もたくさんいます。サービス提供責任者として働いてきた事業所での管理者への転換はもちろん、訪問介護に限らないほかの介護系事業所の管理者などに転職する方もいます。
また、将来的には独立して自分の事業所を持ちたいと考えている方にとっても、人材マネジメント力がつき、たくさんの介護関係者と関われるサービス提供責任者を経験することは、大きなプラスになります。
サービス提供責任者は、訪問介護事業所に必ず置かれる重要な職種です。たくさんのヘルパーとケアマネージャーとの間に立ち、途切れなく、ニーズに見合った、良質な訪問介護サービスを提供するためのキーパーソンとなっています。
高い介護技術・経験を活かし利用者さんに最適なサービスを検討する一方、ケアマネージャーとの連絡やヘルパーの育成、それに書類や事務の処理などもこなし、調整力が問われる責任の大きな職でもあります。
しかし、身体的な負担を減らし、将来のキャリアアップを希望するのであれば、サービス提供責任者の経験は決して無駄にはなりません。要件を満たす方は、サービス提供責任者を目指すことも考えてみてはいかがでしょうか。