
「訪問介護員の一日の流れは?」「訪問介護員は一日に何件訪問する?」
訪問介護の仕事を始めたい方や、転職先を探している方で、このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか?
今回の記事では、訪問介護員の一日の流れや、訪問介護員の一日の訪問件数、一日の訪問件数が多いのに給与が上がらない時の対処法などについて解説します。
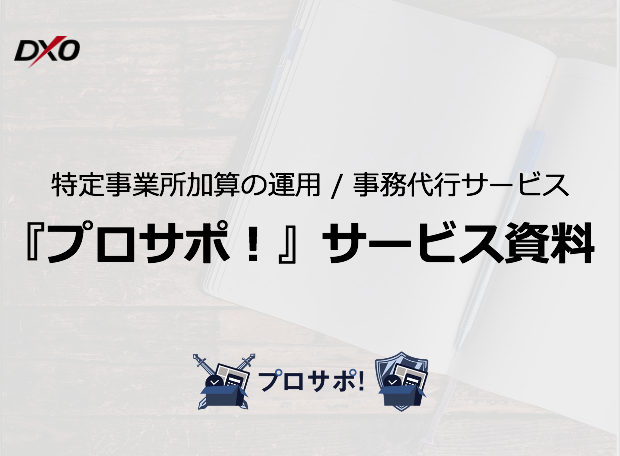
「プロサポ!」は特定事業所加算の運用代行を行うサービスです。
申請書作成及び体制要件の充足を目的とし、申請後に円滑な運用が出来るように支援いたします。
<主な支援内容>
・研修計画の作成&研修システムの提供
・議事録、出席簿の作成
・指示報告システムの提供
・健康診断の受診規定作成
・緊急時案内マニュアルの作成
目次
訪問介護の仕事は主に下記の3つです。
身体介護・・・利用者の体に直接触れて、私生活の援助を行う業務
生活援助・・・私生活での家事全般を援助する業務
通院介助・・・病院や施設に通院している利用者さんの介助を行う業務
訪問介護の仕事内容について詳しくはこちらの記事で解説しています。
訪問介護(ホームヘルパー)ってどんな仕事?具体的な業務内容や1日のスケジュールを紹介!
訪問介護員の一日の流れを、常勤と非常勤の場合それぞれ紹介します。
常勤の訪問介護員(ホームヘルパー)の一日の流れの例は下表の通りです。
| 時間 | 行動 |
| 9:00 | 出勤、本日訪問する利用者さんの情報確認と準備 |
| 9:30~10:00 | 移動 |
| 10:00~11:00 | Aさん宅で生活援助を提供 |
| 11:00~11:30 | 移動 |
| 11:30~12:30 | Bさん宅で身体介護を提供 |
| 12:45 | 帰社 |
| 12:45~13:45 | 昼食、休憩 |
| 13:45~14:00 | 移動 |
| 14:00~15:00 | Cさん宅で身体介護を提供 |
| 15:00~15:30 | 移動 |
| 15:30~16:00 | Dさん宅で身体介護を提供 |
| 16:00~16:20 | 移動 |
| 16:20~17:20 | Eさん宅で生活援助を提供 |
| 17:30 | 帰社 |
| 17:30~18:00 | 記録、引継ぎ |
| 18:00 | 退勤 |
常勤者は基本的に一日中外に出て、利用者宅を訪問している場合が多いです。
早朝の支援が入っていると、常勤者も利用者宅に直行することがあります。
また訪問介護では、サービスの時間が決まっているので、オーバーしないように支援をしていかなければなりません。
利用者さんの話しが終わらず仕事が進まないこともあります。
話しを聞きながらも手を止めず、支援をしていくなどスキルが必要となってきます。
訪問前の利用者さんの情報確認は重要となります。
特にがんの末期や難病をかかえている利用者さんは、急に体調が悪化することがあります。
訪問ごとに体調の変化をチェックし、事業所全体で情報共有を行うことが大切です。
サービス実施記録も重要な業務の一つとなります。
「どんな支援をしてきたのか、利用者さんの様子はどうだったか」など記入をすることで、次のサービスに活かすことができかつ、他の介護サービスのスタッフが見ることで情報の共有ができます。
常勤の訪問介護員は、非常勤の訪問介護員のピンチヒッターになる場合もあります。
急な体調不良や用事で仕事ができなくなった場合、常勤者が代わりに訪問することになります。
非常勤の訪問介護員(ホームヘルパー)の一日の流れの例は下表の通りです。
| 時間 | 行動 |
| 12:30 | 自宅から利用者さん宅へ直行 |
| 13:00~14:00 | Aさん宅で身体介護を提供 |
| 14:00~14:30 | 移動 |
| 14:30~15:30 | Bさん宅で生活援助を提供 |
| 16:00 | 利用者さん宅から自宅へ直帰 |
非常勤の訪問介護員の場合、自宅から利用者宅への直行と、利用者宅から自宅への直帰が多くなるでしょう。
そのため、利用者さんや支援内容に変化がないか、事業所に確認する必要があります。
毎朝本日の訪問予定を事業所に電話をし、月曜日には1週間分の予定を電話します。
2重チェックで漏れのないようにしている事業所もあります。
訪問介護員が一日に何件訪問するのか、常勤と非常勤それぞれの場合について、解説していきます。
常勤の場合、1日全体の訪問件数は5件前後になります。
内訳は午前が2件、午後が2〜3件ほどです。
もう少し多い件数を訪問できそうにも感じますが、訪問介護は利用者宅へ訪問するために1件ごとに移動時間がかかるため、5件が平均になります。
ただし、事業所によっては7〜8件ほど訪問するところや、若い訪問介護員が中心だと10件以上訪問するところもあります。
そのため、訪問件数を重視して仕事を探す際は、事業所のヘルパーの年齢構成も重要なポイントとして、頭に入れておきましょう。
非常勤の場合は、次の2つの働き方に分けられます。
・フルタイム
・空いた時間で勤務する
フルタイムで働く場合は、常勤と同様1日5件前後の担当と考えて良いでしょう。
一方、火曜午後の休みだけといったように、空いた時間で勤務する場合は、1日1〜2件ほど訪問をする方が多いようです。
注意しておきたいこととして、訪問回数を増やしたい場合でも、労働を希望する時間と利用者の希望時間が合わないことがあります。
また、短時間だけの勤務であれば、移動や休憩の時間も考えると、訪問件数を増やすことは難しいでしょう。
一日の訪問件数が多いのに給料が低い時の対処法として、下記の3つが挙げられます。
①移動時間を少なくする
②資格・移動手当のある事業所を選ぶ
③身体介護を積極的に行う
それぞれ解説していきます。
訪問介護で1件でも多く回りたい場合は、距離や移動手段を考える必要があります。
距離は、1件1件の距離間隔が長い場合や、効率の悪い回り方をしてしまうと多く回れません。
また、移動手段は徒歩や自転車で訪問している場合は、移動範囲が限られてしまいます。
その上、移動時間もかかってしまうため、訪問件数を増やすのは難しくなります。
一方、バイクや車を利用している場合は、移動距離が長くても短時間で移動ができるため、多く回れる確率が高くなります。
訪問介護も一般の企業と同じように、事業所ごとに基本給や各種手当、福利厚生などが変わってきます。
今から訪問介護を考えている方は、時給以外にも、資格や移動の手当がある事業所を選ぶと、効率よく稼げるようになります。
また、資格手当がある事業所は、スキルアップできる環境が整っている事業所である可能性が高いです。
スキルアップは、給料アップにもつながってくるため、求人募集の詳細はチェックしておきましょう。
現在訪問介護事業所で働いている方は、あなたの業務内容と給料や待遇が見合わないと感じているのなら、転職を検討してみても良いでしょう。
ホームヘルパーの給料は、調理・洗濯などの家事全般をサポートする生活援助より、入浴・排せつ・食事などの介助を行う身体介護の方が、高めに設定されています。
事業所にも違いはありますが、身体介護の方が生活援助より、時給にして300円ほど高い傾向です。
そのため、生活援助のみ担当している場合は、件数が多くても稼げなくなってしまいます。
現在、生活援助を中心に仕事をしている方は、事業所に身体介護の業務を中心に担当することができないか相談してみると良いでしょう。
また、訪問介護員が給与を上げる方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。
訪問介護の給料相場はどのくらい?正社員か非常勤で給与はどう違う?
訪問介護員に関するQ&Aをまとめました。
訪問介護員に必要な資格として、下記の3つが挙げられます。
①介護職員初任者研修・・・介護業務を行うための基本的な知識や技術を持っていることを保証する資格
②介護福祉士実務者研修・・・高度で専門的な介護知識や技術を持っていることを保証する資格
③介護福祉士・・・介護の知識や技術に関して高い専門性があることを保証してくれる資格(国家資格)
それぞれの取得方法などについてはこちらの記事で詳しく解説しています。
訪問介護に必要な資格3選!メリット・費用・取得方法をご紹介
訪問介護員の正社員の平均的な給与は約31万円です。
訪問介護員の給料について、他の介護施設との給与比較など、こちらの記事で詳しく解説しています。
訪問介護の給料相場はどのくらい?正社員か非常勤で給与はどう違う?
訪問介護員に向いている人の特徴として、下記の5つが挙げられます。
①コミュニケーション能力がある人
②責任感がある人
③些細なことに気づける人
④臨機応変に対応できる人
⑤健康で体力がある人
訪問介護員に向いている人の特徴については、こちらの記事で詳しく解説しています。
訪問介護に向いている人・向いてない人の特徴は?やりがいは?
訪問介護員を辞めた理由として、下記の6つが挙げられます。
①給与に対する不満
②利用者との人間関係の悩み
③移動の負担
④一人で介護する時の責任・プレッシャー
⑤訪問先の環境が良くない
⑥ステップアップの為
訪問介護員を辞めた理由について、詳しくはこちらの記事で詳しく解説しています。
訪問介護を辞めた理由は?最初にするべきこと・対象方法を徹底紹介
訪問介護は日中の仕事のように思われるかもしれませんが、夜間の仕事もあります。
夜間や深夜の支援は、服薬介助やおむつ交換、体位交換、就寝介助をすることが多いです。
定期巡回・随時訪問サービスを行っている事業所では、夜間でも定期的に訪問をしているので夜勤はあります。
厚生労働省の介護保険最新情報によると、令和2年3月に「訪問介護における移動時間は、原則として労働時間に該当する」と通達が出ています。
事業所としてこの移動が「仕事をするために必要な時間」という指示を出せば労働時間に該当するということになります。
例えば、事業所から利用者宅への移動、利用者宅から次の利用者宅への移動などが該当します。
ただ、自由利用が可能な時間と判断される場合は、労働時間には含まれないので注意が必要です。
参考:厚生労働省
今回の記事では、訪問介護員の一日の流れや、訪問介護員が一日に何件訪問するのか解説しました。
事業所によって働き方も変わってくるので、転職先を探している方や、訪問介護員に新しくなりたい方は、今回の記事を参考に、しっかりと下調べをしましょう。