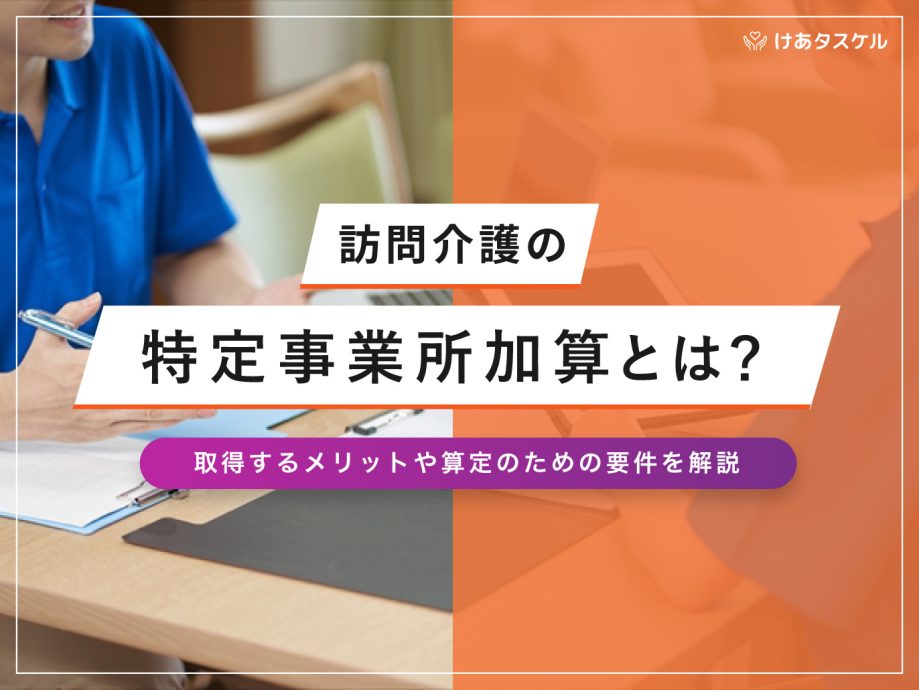
訪問介護の特定事業所加算を取得することで、さまざまなメリットがあります。今回は、そのメリットや算定するための要件について紹介します。ぜひ、最後までお読みください。
目次
訪問介護サービスにおける特定事業所加算は、2024年度の介護報酬改定にて報酬区分や算定要件の見直しが行われる見込みです。
主な変更点は以下の5つです。
改定後の報酬区分や算定要件については、本記事内にて解説しているのであわせてご確認ください。
また、2024年の介護報酬改定について情報を得たい方は以下の記事もあわせてご確認ください。

【2024年介護報酬改定】改定ポイントまとめ|最新情報を元に一覧で徹底解説
特定事業所加算は要介護度の高く、支援が困難な利用者の場合において、専門性の高い従業員を多く配置するなどし、質の高い介護サービスを提供することで事業所に対して支払われる加算です。
この特定事業所加算は2006年の介護報酬改定にて創設されましたが、認知度の低さなどから取得する事業所は少ない状況が続きましたが、2021年度の介護報酬改定において、さらに算定単位の見直しと区分が新設され、より多くの算定単位取得が可能となりました。その後、取得率は年々高くなり、近年では全体の40%程度が加算を取得しています。
なお、介護保険では「訪問介護」「居宅介護支援」の事業で特定事業所加算の算定が可能です。
以下で紹介する加算率や算定要件は、2024年4月1日施行予定の介護報酬改定による変更点を反映したものになります。
現行の算定要件と異なる場合がございますのでご注意ください。
また2024年4月1日の介護報酬改定に伴う変更点は赤字で記載を行っています。
訪問介護の特定事業所加算は下記の5つに分類されます。
算定要件はそれぞれ以下の通りです。
算定要件 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
1.訪問介護員等・サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2.利用者に関する情報またはサービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3.利用者情報の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4.健康診断等の定期的な実施 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5.緊急時等における対応方法の明示 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6.病院、診療所又は訪問看護ステーションの看護師との連携により、24時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて訪問介護を行うことができる体制の整備、看取り期における対応方針の策定、看取りに関する職員研修の実施等 | △*¹ | △*¹ |
| ||
7.通常の事業の実施地域内であって中山間地域等に居住する者に対して、継続的にサービスを提供していること |
|
| 〇 | ||
8.利用者の心身の状況またはその家族等を取り巻く環境の変化に応じて、訪問介護事業所のサービス提供責任者等が起点となり、随時、介護支援専門員、医療関係職種等と共同し、訪問介護計画の見直しを行っていること |
|
| 〇 | ||
9.訪問介護員等が以下のいずれかを満たす
| 〇 | △*² | |||
10.全てのサービス提供責任者が以下のいずれかを満たす
| 〇 | △*² | |||
11.常勤のサービス提供責任者を配置し、基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を1人以上配置 | △*³ | △*³ | |||
12.訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の占める割合が30%以上 | △*³ | △*³ |
| ||
13.利用者のうち、要介護4以上、日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・M、たんの吸引等を必要とする利用者の占める割合が20%以上 | △*¹ | △*¹ | |||
14.看取り期の利用者への対応実績が1人以上であること | △*¹ | △*¹ |
|
*¹:算定要件13または算定要件6および14を満たす場合に算定可能
*²:算定要件9または算定要件10を満たす場合に算定可能
*³:算定要件11または算定要件12を満たす場合に算定可能
※従来の算定要件6「サービス提供責任者ごとに作成された研修計画に基づく研修の実施」は、2024年4月1日施行予定の介護報酬改定に伴い、算定要件1に統合されました。
※従来の算定要件12「利用者のうち、要介護3以上、日常生活自立度Ⅲ・Ⅳ・M、たんの吸引等を必要とする利用者の占める割合が60%以上」は、2024年4月1日施行予定の介護報酬改定に伴い、削除となりました。
下記が特定事業所加算を取得するメリットです。
特定事業所加算の特徴として、総単位数から何%かが加算されます。特に最も加算率が高い「特定事業所加算Ⅰ」を取得すれば、総単位数プラス20%と他の加算に比べて高く、取得するだけで事業所の収益が大きく向上します。
また、重度者対応要件がなく算定しやすい「特定事業所加算Ⅱ」でも、総単位数プラス10%となるため、訪問介護の月商が150万円の事業所であれば下記のように収益が上がります。
【月商が150万円の場合】
算定要件は細かいものの、取得すれば売上の見込みが立ちやすく、経営の安定を図れます。
特定事業所加算は、質の高いサービスを提供している事業所を評価するための加算になるため、加算を算定している=質の高いサービスを提供する事業所と証明されます。
また、加算を取得するにあたって、個別研修・定期的な会議の開催などが必要なため、算定要件を満たすことで必然的に質の高いサービスを提供できる体制をつくれるため、地域での認知度もさらに高くなるメリットがあります。
一方、下記のようなデメリットもあります。
特定事業所加算を取得するにあたって最も注意が必要なのは「特定事業所加算分の返還」です。
加算を取得するためには、さまざまな要件が必要になるため、算定要件の理解が不足していると運営指導で思わぬ指摘を受け、加算の返還を求められる場合があります。
なお、運営指導時に1人でも運営基準減算が見つかれば、全員分が返還になるため、多額の返還金が発生することも珍しくなく、数百万〜数千万円の返還を求められた事例も少なくありません。
特定事業所加算Ⅰを取得すれば20%、加算Ⅱであれば10%利用者の自己負担額が増加します。
そのため、5,000円の自己負担を支払っていた場合であれば、加算Ⅰの取得で1,000円、加算Ⅱの取得で500円の負担が増えるだけでなく、場合によっては介護サービスを受けることができる区分支給限度基準額を超えるケースもあります。
特定事業所加算は算定して終わりではなく、届出後も要件を満たし続ける必要があります。そのため、研修、指示・報告、人材要件の割合計算など、どうしても業務負担が強くなることは否めません。
もし、要件要件を満たさなくなった場合は加算の変更・廃止を届け出ることになるため、自主点検も必要です。少しでも業務負担を減らすために、オンライン動画研修サービスなどのICTを取り入れるのもひとつの方法です。
実際に特定事業所加算を取得したい場合は下記の手順で進めます。
加算要件の詳細はそれぞれ異なります。そのため、もし書類に不備があったり、不正に介護報酬を受給していたりする場合は、介護保険請求の時点で届出の修正・取り消し、もしくは返戻をなる場合があるため、届出を行う前に再度算定要件を満たしているのかを確認しましょう。
また、介護報酬は基本的に3年に1回の頻度で改定されるため、加算の要件に合致しているかどうかの確認は毎年行う必要があります。
届出先は、管轄する市区町村により異なります。また、提出方法は直接書類を窓口へ持参する、もしくは郵送にて書類を送るなどの方法を取ることが可能です。
さらに申請期限は加算を算定する月の前月末日まで、または前月15日までに届出が必要です。ただし、介護職員処遇改善加算の場合は、加算算定月の前々月の末日までに提出する必要があるため、4月から加算を取得したい場合は、2月末までに提出する必要があります。
ただ、管轄している市区町村によってサービス種別ごとに提出書類や提出期限が異なる可能性があるため注意が必要です。
届出する書類は、加算項目・市区町村によって異なりますが、基本的には下記の2種類です。
この中で、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」は、届出を行う事業所の施設名や住所、サービス種別などの基本情報を記載する書類です。
一方、「体制等状況一覧表」は、現在の事業所の区分や人員配置区分を記載し、加算算定状況などを記載しますが、市区町村により提出する書類が異なる場合があるため、各都道府県や市町村のホームページを確認し、提出漏れがないよう注意しましょう。
届出が受理され、算定開始となっても下記の場合は、各加算の届出が必要な場合があります。
上記のような場合は、速やかに加算の届出が必要になる場合があります。
参考:千葉県「加算等に関する届出について|介護サービス事業者の方へ」
今回は、訪問介護の特定事業所加算を取得するメリットと算定要件を解説しました。特定事業所加算は、質の高い介護サービスを提供することで事業所に対して支払われる加算になるため、取得していることで地域での認知度が高くなります。
それだけでなく、特定事業所加算Ⅰであれば、総単位数の20%プラスという事業所の収益を安定的に上げられるだけでなく、特定処遇改善加算Ⅰも取得が可能になります。従業員の確保にもつながり、安定した事業所運営を継続できるようになるため、取得すべき加算の1つです。