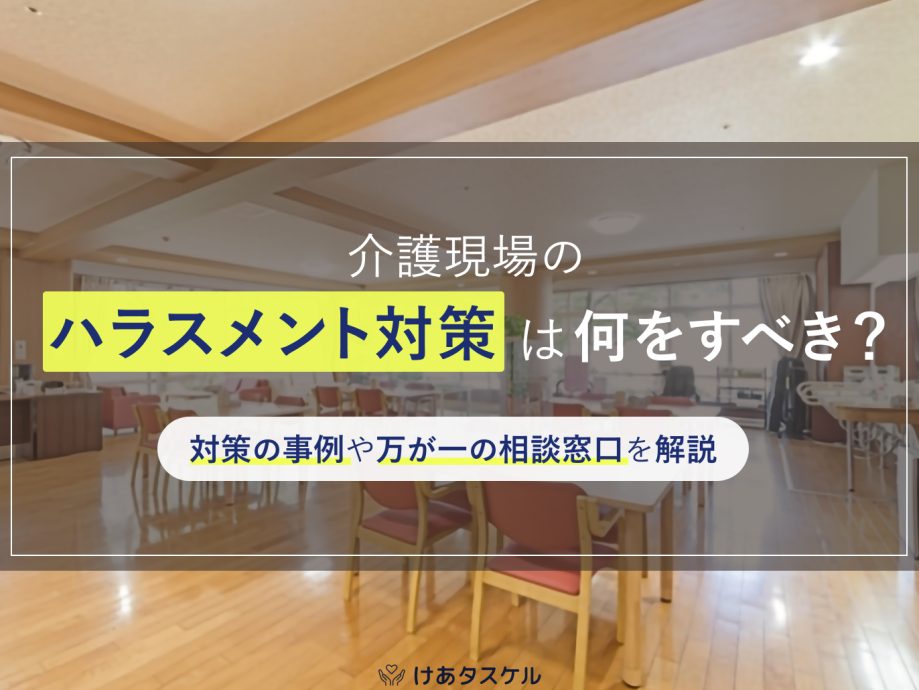
近年、介護サービスの利用者やその家族から介護職員へのハラスメント行為が度々発生しています。このような背景から2021年度の介護報酬改定にて、ハラスメント行為への対策強化を目的に、ハラスメント対策として必要な措置を講じることが介護事業者に義務付けられました。しかし、具体的にどのような対策をおこなえばいいかわからず、まだ十分な対策がおこなえていないとお悩みの事業者も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、介護現場におけるハラスメント対策を具体的に解説します。ハラスメント対策の具体的な事例やハラスメント行為への相談窓口についても紹介するのでぜひ参考にしてください。
目次
介護現場におけるハラスメント対策は2021年4月1日から義務化されています。
2021年度の介護報酬改定において、介護職員の処遇や職場環境の改善に向けた取組を推進する観点から、全ての介護サービス事業者を対象にハラスメント対策を講じることが義務化されました。
なお、ハラスメント対策を講じることは介護現場以外でも求められており、セクハラについては男女雇用機会均等法にて、パワハラについては労働施策総合推進法にて、大企業で2020年6月1日、中小企業では2022年4月1日から義務付けられています。
【男女雇用機会均等法】
第十一条
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
引用:e-Gov法令検索「昭和四十七年法律第百十三号 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」
【労働施策総合推進法】
第三十条の二
事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
引用:e-Gov法令検索「昭和四十一年法律第百三十二号 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」
介護現場におけるハラスメント行為は、利用者もしくはその家族からによるハラスメント(カスタマーハラスメント)と、職員間で発生したものの2種類に大きく分けることが可能です。
この中でもカスタマーハラスメントは大きな問題となっています。厚生労働省の「介護現場におけるハラスメントに関する調査研究 報告書」によると、施設や事業所に勤務する職員のうち、カスタマーハラスメントを受けた経験のある職員は、利用者からでは4~7割、家族などからでは1~3割もいることがわかりました。
ハラスメント対策を適切におこなうためには、どのような行為がハラスメント行為といえるのか、明確な定義を把握しておくことが大切です。以下ではハラスメント行為の種類について、利用者やその家族からによるものと職員間によるものの大きく2つにわけて紹介いたします。
カスタマーハラスメントでよくみられるものは以下の通りです。
利用者やその家族からの介護職員に対する身体的暴力は、立派なハラスメント行為といえます。
具体的な行為としては、叩く蹴る・殴る・ひっかくなどの身体的な攻撃行為から、物を投げつける・唾を吐くといった間接的な攻撃があてはまります。
精神的暴力とは、言葉や態度によって介護職員の尊厳や人格を傷つけたり、おとしめたりする行為のことを指します。
具体的な行為としては、罵倒や威嚇、脅迫といった直接的なものから、無視をしたり何度も理不尽な要求を繰り返したりといった間接的なものがあてはまります。
セクシャルハラスメント(以下セクハラ)は、意に添わない性的誘いかけや性的ないやがらせ行為のことを指します。
セクハラの具体的な行為としては、性的な発言や不適切な言葉の使用、手や身体を触るなどの身体的な接触、または性的な不適切な要求をおこなうといったものがあげられます。
職員間のハラスメント行為でよくみられるものは以下の通りです。
パワーハラスメント(以下パワハラ)は、地位や優位性を利用して苦痛を与え、職場環境を悪化させる行為のことを指します。なお、パワハラとしての定義を満たすためには、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
【パワハラの3つの定義】
職員間においてもセクハラがおこなわれる可能性があります。
職場における地位や優位性を利用したパワハラと組み合わせたハラスメント行為がおこなわれることもあります。
マタニティハラスメント(以下マタハラ)は、妊娠・出産などを理由に、育児介護ハラスメントは育児や介護に関する制度の利用を理由におこなわれるハラスメント行為です。
具体的な例としては、制度として認められている産休や育休の利用を批判したり、体調や家庭環境を加味しない無理な仕事量を押し付けたりといったことがあてはまります。
介護現場におけるハラスメント対策には以下の5つがあげられます。とくに1つ目と2つ目は義務化された内容なので詳しく確認しておきましょう。
ハラスメント対策のうち義務付けられている対応の1つ目は、ハラスメント対応の方針を明確化し、周知・告発をおこなうことです。
具体的な対応としては、職務規程を定めた文書などでハラスメントをおこなってはならない旨の方針を規定したうえで職場内で周知をおこなうことや、ハラスメント行為についての研修・講習などを実施することがあげられます。
また、職場でハラスメント行為をおこなった人に対して厳正に対処する旨を定め、職員に周知・啓発することも必要です。
ハラスメント対策のうち義務付けられている対応の2つ目は、事業所内に相談窓口を設置することです。相談に対応する担当者をあらかじめ定めたり、相談に対応するための制度を設けたりすることが求められます。
また、窓口や制度を設けるだけではなく、相談内容や状況に応じた適切な対応が取れる体制を作ることも必要です。対応例としては、相談窓口と人事部門の連携や相談を受けた際の対応についての研修をおこなうことなどがあげられます。
以降紹介するハラスメント対策は義務化されているものではありませんが、ハラスメントを防止するにあたって非常に大切な考え方・方針です。ぜひ確認のうえ事業所におけるハラスメント対策にお役立てください。
ハラスメント対策をおこなうためには、まずハラスメント行為に対する正しい理解を持つことが大切です。介護職員に対しておこなわれた行為がハラスメントと呼べるか否かの判断は、客観的な視点をもっておこなわれる必要があるため、ときにはハラスメントとはいえない場合もあるでしょう。
ただし、ハラスメントの判断は客観性をもっておこなう必要があるものの、行為や言動を受けた介護職員に寄り添うことも重要です。のちに行為や言動がエスカレートし、ハラスメントと呼べる状態になったとしても、問題をひとりで抱え込んでしまう恐れがあります。日頃からおかしいと感じたものに対して、相談・サポートをおこなえる体制や関係性を設けたり、研修をおこなうことでハラスメントへの理解を深めたりといった対策をとっていきましょう。
ハラスメントの対策には初期対応が非常に重要です。初期対応を誤ってしまった結果、利用者との関係性が悪化したり、ハラスメント行為がエスカレートしてしまう可能性が考えられます。
また、適切な初期対応を取るためには、ハラスメントがなぜ発生したか要因を分析をすることも大切です。とくに以下のようなリスク要因を減らすことで、事前にハラスメント行為を予防することにもつながるでしょう。
【ハラスメントのリスク要因】
利用者やその家族からのハラスメント行為がひどい場合は、やむを得ず契約解除を検討するのもひとつの選択肢といえます。ただし、契約解除をおこなうためには正当な理由が求められることに注意してください。
ハラスメント行為による契約解除が認められるかどうかは、以下の要素などをもって判断されます。
介護現場においてハラスメント対策をおこなう際は以下のポイントにも注意して対策を講じるようにしましょう。
ハラスメント行為を対策するためには、ハラスメント行為を受けた職員がひとりで悩まないように注意する必要があります。ハラスメントによる問題が生じた際には、相談窓口や職員間で共有できる場を設け、適切な議論をおこなえる体制を作るようにしましょう。
ハラスメント行為を対策する際には、相談や報告を受けた管理者がひとりで抱え込まないようにする必要もあります。
ハラスメント行為に対して管理者がひとりでおこなえる対策には限界があります。必要に応じて地域の多団体や機関との連携を取ることや、時には弁護士などの専門家や警察などへ協力を仰ぐことも検討しましょう。
BPSDとは、認知症の方にみられる行動面・心理面の症状のことを指し、具体的には徘徊や攻撃的な行動、不適切な性的行動などがあげられます。
BPSDの具体的な行動の中には、一見するとハラスメント行為と判断できてしまうものが存在します。認知症の利用者によるこのような行動が見られた際には認知症ケアが必要となること、また行為や言動を受けた職員への対応に注意するようにしましょう。
介護現場にて適切なハラスメント対策がおこなえるよう、厚生労働省ではハラスメント対策を目的としたマニュアルや事例集、研修のための手引きを公開しています。対策や体制作りを具体的に進める際には必ず確認しておきましょう。
参考:厚生労働省「介護現場におけるハラスメント対策」
介護現場におけるハラスメント対策を進めるためには具体的な事例をもとに検討することが大切です。以下ではハラスメント対策の事例と対策例を紹介します。
1つ目に紹介するのは、介護職員が利用者から暴言や嫌がらせを受けたケースです。
介護職員が利用者から「足が太い」などの身体的な暴言やその他セクシャルな嫌がらせを受けることがありました。利用者は、ハラスメント行為を受けた職員および周りの職員により、行為をやめるよう伝えられていましたが以降も行為は止まらず、職員から管理者に相談がおこなわれました。
職員会議の結果、その職員と利用者が1対1にならないようシフトの調整などをおこったほか、利用者には今後も行為が続くようであればサービス提供が難しくなる旨を説明しました。
その結果、利用者とその家族からは謝罪があり、職員に対するハラスメント行為はおこなわれないようになりました。
参考:厚生労働省「介護現場におけるハラスメント事例集」
次に紹介するのは、利用者から性的な発言や威圧的な言動を受けたケースです。
訪問サービスを提供していた利用者より性的な発言や威圧的な発言がおこなわれることが多々ありました。また、利用者に対して担当者が固定化されないようシフトを組んでいましたが、利用者から特定の職員を拒否する発言があり、シフト調整などの負担が生じる自体となっていました。
このような背景から担当者会議が開かれハラスメント行為に当てはまることを確認し、利用者には今後も行為が続くようであればサービス提供が難しくなる旨を説明しました。その結果、利用者からの過激な発言は少なくなり、サービスの継続を気にするそぶりも見られるようになりました。
本件においては担当していた介護職員が「利用者ご本人のキャラクターだから仕方がない」と我慢していた期間があり、ケアマネジャーへのエスカレーションが遅くなったことが指摘されています。介護職員各々のハラスメント行為に対する理解を深めることが重要とわかる事例といえるでしょう。
参考:厚生労働省「介護現場におけるハラスメント事例集」
介護現場のハラスメントを相談できる窓口はカスタマーハラスメント向けのものと職員間のハラスメント向けのものに分かれます。以下ではそれぞれについて紹介していきます。
介護現場のカスタマーハラスメントについて相談できる窓口は以下の通りです。
東京都社会福祉協議会の弁護士による相談窓口は、介護事業所や介護保険施設の管理者などが利用できる相談窓口です。介護現場におけるカスタマーハラスメントに対して、弁護士への無料相談をおこなえます。
具体的に相談できる内容としては、具体的なハラスメント行為に対する相談のほか、ハラスメント行為を考慮した契約書・重要事項説明書の作成へのアドバイスなどがあげられます。
ただし、利用は都内を所在地とする事業所や施設に限られるため注意してください。
| 介護現場における利用者や家族等からのハラスメント 弁護士による相談 | |
| 電話番号 | 03-3268-7192 |
| メールアドレス | kaigo-harassment@tcsw.tvac.or.jp (所定の相談票の添付が必要) |
参考:東京都社会福祉協議会「介護現場における利用者や家族等からのハラスメント 弁護士による相談」
介護現場における利用者やご家族等からのハラスメント相談窓口は、東京都福祉人材センターによって設けられている介護職員向けの相談窓口です。利用者やその家族から受けたハラスメント行為に対して、相談員への相談を無料で利用できます。
ただし、都内を所在地とする事業所や施設に勤務する職員に利用は限られるため注意してください。
| 介護現場における利用者やご家族等からのハラスメント相談窓口 | |
| 電話番号 | 03-6265-6161 |
| 受付時間 | 平日10:00~17:30 (12/29~1/3を除く) |
参考:東京都社会福祉協議会「介護現場における利用者やご家族等からのハラスメントのお悩み相談」
職員間のハラスメント行為について相談できる窓口は以下の通りです。
福祉のしごとなんでも相談は、東京都福祉人材センターが運営する介護現場で働く職員向けの相談窓口です。仕事や職場への悩みに対して、福祉現場に詳しい相談員が対応します。
相談方法は電話もしくは面談による利用が可能です。面談で相談する場合、予約をおこなうことができるため事前に確認しておきましょう。
| 福祉のしごとなんでも相談 | |
| 電話番号 | 03-5212-5513 |
| 電話相談の受付時間 | 平日10:00~17:30 (12/29~1/3を除く) |
| 来所相談の予約受付時間 | 平日10:00~17:30 (12/29~1/3を除く) |
| 来所相談の受付時間 | 平日10:00~17:30 (12/29~1/3を除く) |
| 来所相談の場所 | 東京都福祉人材センター(飯田橋) …予約なし可、予約優先 東京都福祉人材センター多摩支所(立川) …要予約、17時まで |
参考:東京都社会福祉協議会「都内の福祉職場で働く職員の皆様へ」
総合労働相談コーナーは労働局や労働基準監督署などに設置されている労働問題の総合相談窓口です。問題を直接的に解決してくれるわけではありませんが、解決方法の案内や労働局への取次ぎをおこなってもらうことができ、一人で悩むよりも確実に解決に近づくことが可能になります。
総合労働相談コーナーは各都道府県に複数設置されているため、以下のページより最寄りの窓口を確認し利用を検討してください。
参考:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
みんなの人権110番は法務局に設置されている人権問題に関する相談窓口です。いじめやハラスメント行為に対する相談をおこなえます。
法務局およびその支局では面談による相談も利用ができるため、対面の方が話しやすいという人は利用を検討してみてください。
| みんなの人権110番 | |
| 電話番号 | 0570-003-110 |
| 電話相談の受付時間 | 平日08:30~17:15 |
参考:法務省「常設相談所(法務局・地方法務局・支局内)」
介護現場におけるハラスメント対策を講じることは2021年度の介護報酬改定によって義務化されました。具体的な対応としては、対応方針を明確化し周知・啓発をおこなうこと、事業所内に相談窓口を設置することの2点が求められます。
ハラスメント対策がまだ不十分という事業所や施設の担当者は、本記事や厚生労働省が提示しているマニュアルなどを参考に速やかに対策をおこなうようにしましょう。