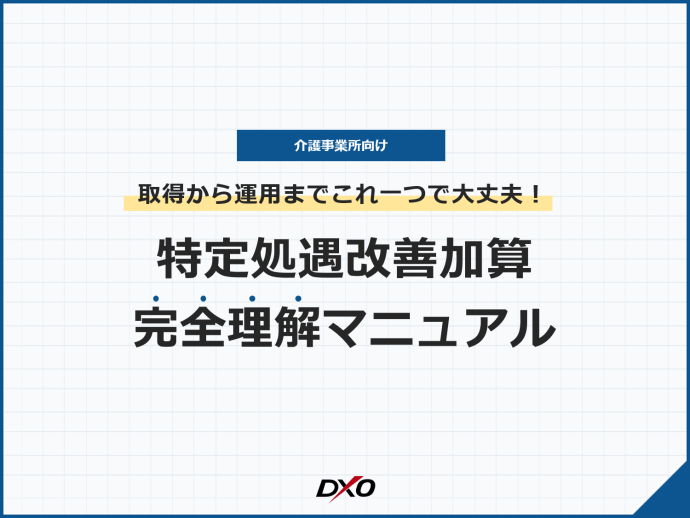介護のお仕事は大変な業務が多いにもかかわらず、高いお給料が望みにくいという印象を持っている方は多いはずです。
しかし介護業界にはさまざまな制度があり、介護職の職場環境改善を図るため、国としてもさまざまな仕組みを整えています。
その一つとして設けられたのが特定処遇改善加算で、所得待遇の改善につながる制度でもあります。
介護職についているなら知っている方は多いでしょうが、今回の記事ではこの特定処遇改善加算とはどんな制度なのかなどを解説していきます。
目次
特定処遇改善加算とは特に経験のある介護に携わっている方の給料を増やすための制度のことです。
介護職というと他業種に比べて収入が低く、離職率が高いお仕事でもあります。
これにより少しでも長く働いてもらい、また介護職の離職率を減らし就職率をアップさせて人材不足を補うといった狙いがあります。
特定処遇改善加算の対象となっているのは経験や技能のある介護職員です。
介護福祉士の資格を所持しており、勤続年数の長いベテラン介護職員がターゲットとなっています。
基本的に勤続年数は10年以上の介護職員が対象になりますが、一つの事業所に10年以上ではなく介護職員として働いた期間をトータルで見ます。
ただし、10年の勤続年数という条件は、特に必須事項というわけではありません。
10年以下の勤続年数でも、経験や技能によっては特定処遇改善加算の対象になり得ます。
また、経営者や事業所によって介護福祉士の資格を持つものがいない場合は、対象者は事業所の裁量で検討でき、特定の条件を満たすことで対象になることもあります。
このため、対象者でなくとも受給できるケースがあるので、まずはお努めの事業所に問い合わせてみるのもいいでしょう。
では特定処遇改善加算はいくらもらえるかですが、これは事業所や経営者の判断で支給額が決定されることもあるので職場によってある程度の差があることをふまえておきましょう。
特定処遇改善加算でお給料がアップしやすいのが「経験・技能のある介護職員」で、平均で約2万円増えるとされています。
また「その他の介護職員」は約1万円、「介護職員以外」では約5千円程の報酬アップが見込まれます。
特定処遇改善加算の計算には、I〜Ⅱの新加算とそれに合わせた加算率を元に以下のように行います。
各事業の介護報酬(処遇改善加算を除く)×各サービスの新加算Ⅰ~Ⅱ=特定処遇改善加算の金額
加算率は事業所の形態で変化しており、以下の表のように分類されます。
新加算Ⅰ(%) | 新加算Ⅱ(%) | |
訪問介護 | 6.3 | 4.2 |
通所介護 | 1.2 | 1.0 |
グループホーム | 3.1 | 2.3 |
特養 | 2.7 | 2.3 |
老健 | 2.1 | 1.7 |
ただし、介護サービスの内容によっては特定処遇改善加算の対象外になるので、正しく計算する際はしっかりチェックしておきましょう。
特定処遇改善加算の配分は、介護職員を3つに分類することから始まります。
1.経験・技能のある介護職員
2.その他の介護職員
3.介護職員以外
各事業所は上記3つの中からどの職員に配分を行うか決定できますが、1の介護職員の内1人以上の月8万円給料アップまたは、年収見込額440万円以上にならなくてはならないルールがあります。
さらに、処遇改善加算額の平均が1は2の2倍以上、3は2の1分の1を上回らないこともルールに挙げられます。
特定処遇改善加算の基本的な情報をまとめましたが、なかなか理解できない部分や細かい箇所の疑問点もあることでしょう。
そこでここでは、特定処遇改善加算についてよくある質問と解答をご紹介します。
特定処遇改善加算が新設された方針として、「勤続年数10年以上の介護福祉士に対し、月8万円相当の処遇改善を実施する」とあります。
このため、制度が設立された当初は「月8万円」が独り歩きして、大きな期待を寄せた方も多いでしょう。
実際は月8万円の給料アップの可能性がありますが、新加算の種類や施設の形態などさまざまな条件の元に計算されます。
当然、自身の勤続年数やスキルによっても金額が変動するので、必ずしも期待できる金額ではないことを理解しておきましょう。
特定処遇改善加算でいくらもらえるかは、前述した通り勤続年数や技能などの条件に合わせて平均5千円〜2万円の収入アップが見込まれます。
前述した通り、特定処遇改善加算の対象者は「勤務年数が10年以上の介護福祉士」となっています。
このため、条件さえ満たしていればパートだけでなくアルバイトも対象者になります。
特定処遇改善加算と処遇改善加算の2つは、言葉だけを並べると「特定」がついているかそうでないかなので違いがわかりにくい印象ですよね。
簡単に言うと、特定処遇改善加算は経験やスキルが豊富なベテラン介護職員向けの制度で、処遇改善加算は介護職員全般に向けた制度です。
どちらも介護職員の報酬改善を目的としていますが、対象者によって扱う制度が違います。
ただし、処遇改善加算については管理者やケアマネジャー、看護師、事務員を対象外にしていますが、介護業務を兼任している場合は対象となるといった細かなルールも設けられています。
特定処遇改善加算は処遇改善加算とともに2019年の施行依頼、介護職員の平均収入アップに貢献する制度として活躍しています。
これにより、他業種に比べて介護業界の収入が低いというイメージを払拭し優秀な人材を一人でも多く確保するなどの、業界にとってプラスの方向に働き始めています。
今後もさまざまな処遇改善が期待されるので、情報はしっかりチェックしておきたいですね。